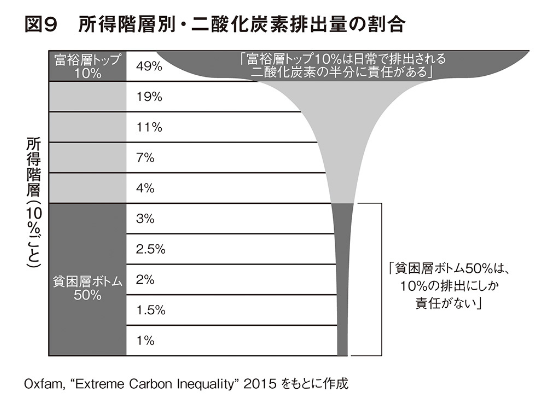物語を渡り歩く B245 『自然の哲学(じねんのてつがく)――おカネに支配された心を解放する里山の物語』(高野 雅夫)
 高野 雅夫 (著)
高野 雅夫 (著)
ヘウレーカ (2021/8/20)
「人新世の資本論」を三分の一ほど読んだ頃、これは里山資本主義的な話につながるのでは?という気がした。
と言っても、藻谷浩介の「里山資本主義」は「流行ってるな」と横目で見ていただけで未読だったので、これは読むタイミングかなと思い購入することにした。
その際、関連書で比較的新しいものも合わせて読んでみようと思い里山で検索して引っかかったこちらも購入。
ただ、タイトルの「じねん」という音のイメージから、求めているような内容とは違うんじゃ、と少し迷った末の、一つの掛けとしての購入だった。
結果として購入した価値があったと思うので、思ったところを書いておきたい。
「自然(じねん)」について
著者は大学で持続可能な中山間地域づくりをテーマに研究しながら、自らも岐阜県の里山に移り住んだ方で、本書は、里山の成り立ちから始まる。
著者の定義では、里山は「人間が草を刈ったり木を伐ったりして自然に介入することによって成立した生態系とその景観」のことを指す。
自然(しぜん)はnatureの訳語として当てられたものだが、もともとはじねんと読み、「自ら然るべきようになる」世界を表す言葉だったそうだ。
里山には昔の人がそうしてきたように、自ら然るべきようになるような生き方の可能性が残されている、ということだろう。
この本を通して感じたことだけど、「自ら然るべきようになる」世界観における「今」は世代・時間を超えた連綿と続くつながりの中での今であり、「私」は個を超えたつながりの中での私である。
翻って、現代の私たちの「今」や「私」は、分断された点としてのそれらのみが視野を覆っている。
そこから大きな歪みが生じてしまっているように感じた。
(ただ、購入する時に躊躇してしまったように、じねんの音は、ぼうぼうと髭をはやした特別な人がやってるような匂いを感じてしまったので、個人的には使い方の難しい言葉のように思っている。理念を伝えつつも、特別なこと、という匂いはできるだけ消すような迂回、もしくはそれを相殺するようなカウンターがどこかで必要な気がする。これは難しいところで単なる個人の印象の問題かもしれないけれども。)
「生国」「村」「日本国」3つのレイヤー
私たちが生きているのは、3つのレイヤー、上から「日本国」(国家社会)、「村」(地域コミュニティ)、「生国(しょうごく)」にまたがっている。私たちが当面する課題は「日本国」の中だけで生きる暮らしから抜け出て、「村」を経由して「生国」に還るということだ。(p.201)
生国という言葉は水俣病に関する運動をされていた緒方正人氏が苦悩の末にたどり着いた言葉で命のつながりの中で生きる、というようなことだと思う。(これについては別の機会に書きたい)
先のじねんの話と同様に、都市部では「日本国」のレイヤーに覆い尽くされてしまっていて、「生国」を感じながら生きることが難しくなっている。
私は子供時代を奈良の田舎と屋久島で過ごしたけれども、あの時に感じていた自然とのつながりやそれが失われていくことに対する感情が、今はかなり鈍くなってしまっていることを感じる。
引っ越しを繰り返してきたことや子供時代をここで過ごしていないことも関係あると思うけれども、自分が住んでいるところに対する愛着を感じにくくなってしまっていることと、その場所がどういうレイヤーにあるかということは関連しているように思う。
父は、奈良で電子部品をつくる会社でサラリーマンをしていたけれども、私が中1の時に突然会社を辞め、家族で屋久島に移住して農業を始めた。
思えばこれも、生きるレイヤーを変えたかったのかもしれない。(そして、今、自分がその時の父の年齢に近い。)
子どもたちへ
先程、住んでいるところに対する愛着を感じにくくなってしまっている、と書いたけれども、子どもたちはどうだろうか。
3つのレイヤーとそれぞれ関わりが持てているだろうか。一つの価値観での振る舞いばかりを押し付けてしまっていないだろうか。
彼らは将来ここを故郷と感じられるだろうか。(屋久島を故郷のように感じて欲しいとも思いながら、コロナの関係で長く連れて帰ってあげられていない。)
そう考えると少し心もとない。
森のようちえんを例に出した後に、著者は次のように書いている。
そのようにして育った子どもが中学、高校になると受験競争に巻き込まれていくのが私はなんとももったいないと思う。森のようちえんの中学・高校版を作りたい。自分が興味のあることについて地域の大人たちから専門的なことを学び、スキルを身につけ、地域の中で一人前として働き暮らすことができるようになるための学びの場だ。学問に目覚めれば大学に行けばよいが、そうでなければ、一度は外に出て世界を旅してくる。そのうえで地域の中で働き暮らし、地域を支える人になる。私はそういうライフコースが、田舎で生まれ育った子どもたちの普通の姿になる日を夢みている。(p.178)
この部分に著者の思いが凝縮されているように感じた。
以前も書いたけれども、屋久島に引っ越して印象的だったのが、同級生たちが何でも自主的に動く姿で、自分がひどく子供じみて思えて情けなかった記憶がある。
彼らがあんなに逞しくみえたのは、おそらく、島の生活の中で子どもたちも大人と同じように扱われることが多かったからだろう。
私がその後生きていく上で力になったことの多くは、屋久島で父の農業を手伝う中で学んだように思う。(移住してまず手伝ったのが、使われなくなったビニールハウスを解体してきて、家の農地に組み立て直すところからだった。移住するまでは、父は週末たまに家にいる人、という感じの関わりだったので、かなり大きな変化である。)
自分は子どもたちにそういう機会を与えられているだろうか。
物語を書き換える→渡り歩く ポストモダンの作法
統制が可能になるのはなぜか。ユヴァル・ノア・ハラリのベストセラー、『サピエンス全史』(2016年)の中心的な議論の一つが、人間は想像力によって目の前にいない大勢の人間と共同・協力ができるということだ。共通の物語を信じることができ、これによって大規模な共同・協力ができる。これが他の動物にないホモサピエンスの特質であり、人間が文明を作り上げてきた要因だというのがハラリの主張だ。(p.57)
この想像力は「生国」「村」「日本国」それぞれのレイヤーで人を結びつけてきたが、現在は「日本国」レイヤーの資本(おカネ)と科学の2つの物語が主流で、私たちの繁栄を生み出すとともに、私たちを強力に縛っている。
著者は、これらが私たちの心の中にある物語に過ぎないのであれば、物語を書き換えてしまえば良いと言う。
環境や経済の問題を考える時、それが理論的に正しいか正しくないか、ということについ囚われてしまう。それが全て悪いとは思わないが、そこに囚われている限りは、その物語の中でしか思考したり感じることはできなくなってしまう。
資本の物語も科学の物語も、無数にある物語の一つでしかなく、たまたま現在はそれが主流になっているにすぎない、もしくはたまたまそれを物語の位置に置いているにすぎない、と一旦距離をとってみる。
その上で、資本や科学の物語が必要であれば召喚すればよいが、そうではないレイヤーの物語も手札の中に持っておく。そういうポストモダンの作法によって強力な物語から少しは自由になれはしないだろうか。
物語は縛られるものではなく、自在に操るものである方がおそらく生きやすい。
■オノケン│太田則宏建築事務所 » 歴史も物語も別様でありえるということを知りつつ肯定とともに選択する B215『ゲーム的リアリズムの誕生~動物化するポストモダン2』(東 浩紀)
歴史も物語も別様でありえるということを知りつつ肯定とともに選択する、という能動的な態度を通じて世界と向き合ってみる。その態度によって初めて接続可能なリアリティというものがあるように思うし、その先では妄想を物語へ転換するための知識や技術、言葉が、新鮮で豊かな色彩を帯びたものに見えてくるのではないだろうか。
それは、モートンの姿勢に通ずるものがあるような気がする。(モートンは紹介本でしか読めてないけれども)
■オノケン│太田則宏建築事務所 » あらゆるものが、ただそこにあってよい B212『複数性のエコロジー 人間ならざるものの環境哲学』(篠原 雅武)
モートンの思想が理解できたわけではないが、彼の言うエコロジーは自然礼賛的な環境保護思想とは全く異なるもののようだ。
モートンはモダニティ、自然や世界、環境と言った概念のフレームや構造的な思考自体が失効し、その次のエコロジカルな時代が始まっていると言う。
エコロジーについて思考すると言っても、自然や環境といった概念的なものを対象とするのではなく、身の回りの現実の中にあるリアリティを丁寧に拾い上げるような姿勢の方に焦点を当て、エコロジカルであるとはどういうことかを思索し新たに定義づけしようとしているように感じた。
それは、近代の概念的なフレームによって見えなくなっていたものを新たに感じ取り、あらゆるものの存在をフラットに受け止め直すような姿勢である。と同時に、それはあらゆるもの存在が認められたような空間でもある。
そのためには、やはりいろいろなレイヤーに身を置いてみることも必要だと思うし、ここでは深堀りしないが、著者は里山にその可能性を見たのだろう。
それでも田舎にやってくれば「いのち」の物語を体感できるチャンスは豊富にある。そのような経験を通して、「おカネ」と「何でもできる自分」の物語を薄め、自然(じねん)と「ご縁」の「いのち」の物語に書き換えていくことができる。そこに田舎の美しさがあるのだと思う。(p.229)
じねん、ご縁、いのち・・・それらは「村」と「生国」のレイヤーの言葉であり、そこでの実感がなければ本当に伝えることは難しい。(なので、この記事では「この本に書かれている「村」と「生国」に関することを伝える」ことを目指さなかった。)
その壁を乗り越えて伝わるものにするには、やはり物語を自在に操り、いろいろな物語を行き来するような越境者、自在な者であることが必要なのかもしれない、という気がしている。


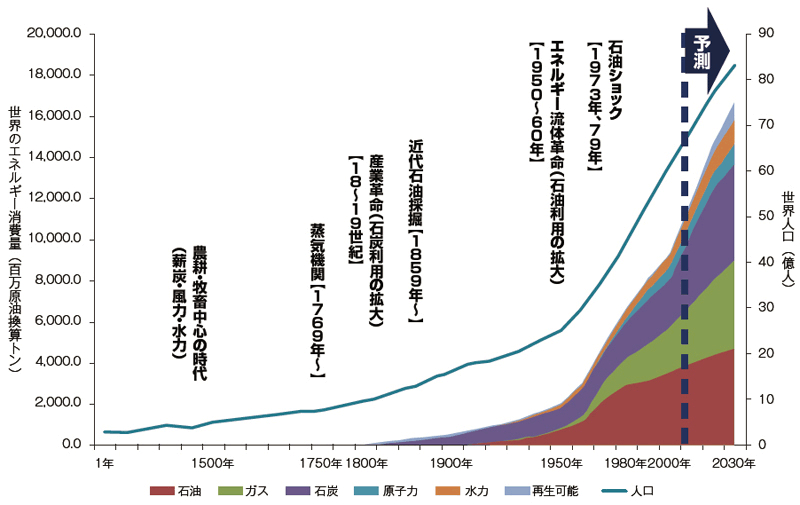 (
(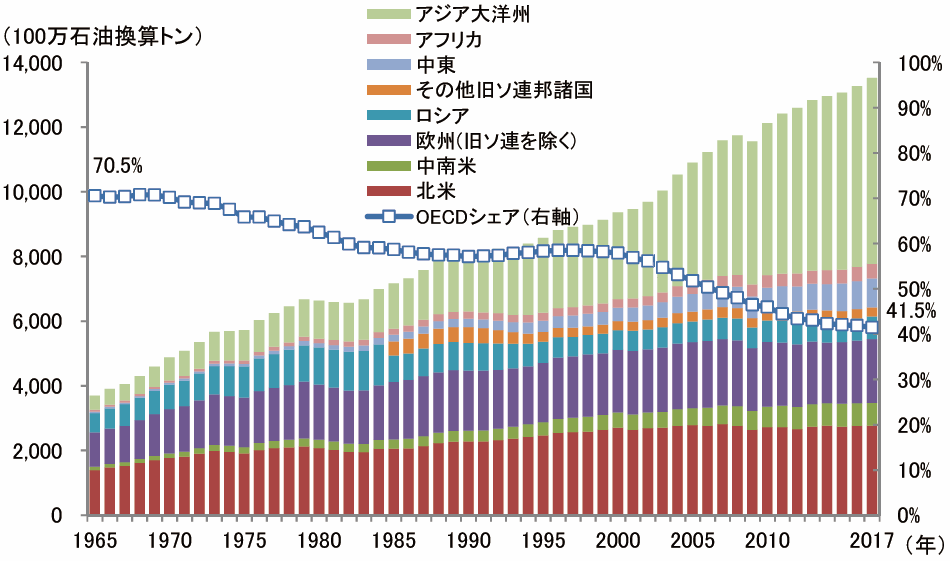 (
(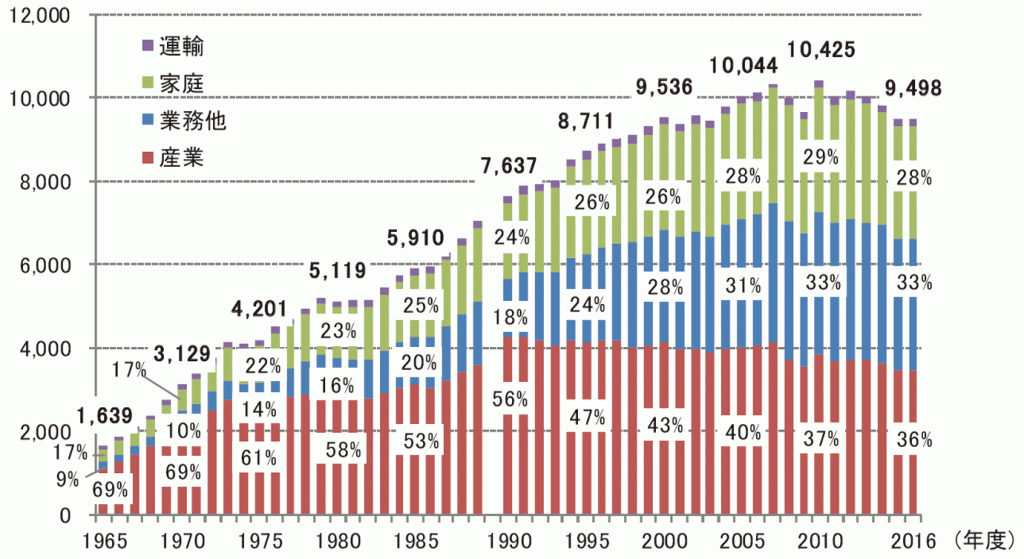 (
(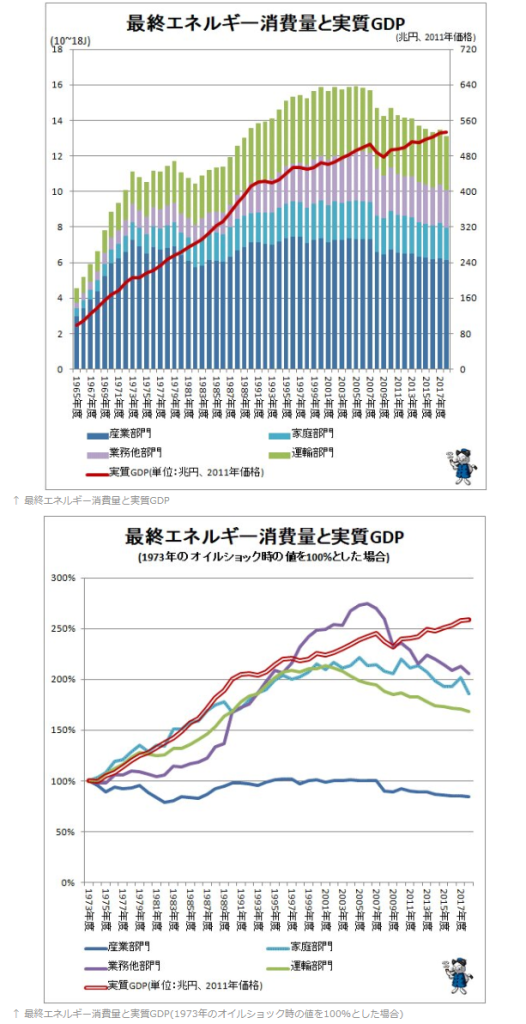 (
(