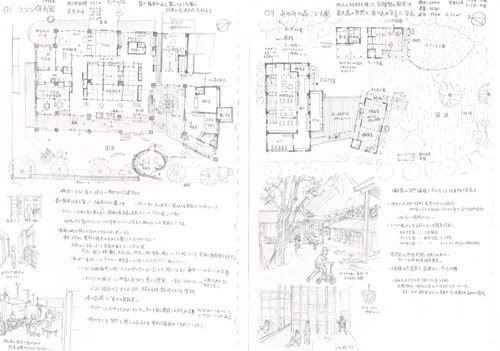脆弱性を受け入れ隙間を捉える B207『公共空間の政治理論』(篠原 雅武)
 篠原 雅武 (著)
篠原 雅武 (著)
出版社: 人文書院 (2007/8/1)
だいぶ前に『アトリエ・ワン コモナリティーズ ふるまいの生産』で紹介されていた本から数冊購入したのですが、これはそのうちの一冊。
本書で考えてみたいのは、共通世界としての公共空間とは何かということであり、また同時に、これがなくなりつつあるのではないか、そうであるならどうしたら良いのかということである。(p.4)
帯には「公共空間の成立条件とは何か?」「アーレント、ルフェーブルの思想をたどり、公共性への問いを「空間」から捉え返す、現代都市論・社会理論の刺激的試み。」とあります。
公共空間が失われつつあるのではないか、という問いかけ自体は目新しいものではないと思いますが、「空間」から捉え返すとはどういうことか、アーレントからどう展開されるか、また、古びた問いをどう展開するのか、にも興味がありました。
一度目は細切れでしか読めず、ぼんやりとしか掴めなかったので、二度目を読みながら並行して、自分なりにまとめていきたいと思います。
序章
まずは序章から。
序章では、公共空間を考えるためのいくつかの視点・問いが提示されます。
公共空間とは何か。
公共空間とは何か。
ここではアーレントの公共空間に関する議論とジンメルの空間の捉え方を参照しているのですが、公共空間とは、空虚でしかなかった空間が、隣人との相互行為によって「あいだ」が満たされることで意味ある何かとして現れた空間のことである、と言えそうです。
この相互行為によって「あいだ」満たされた状態をどうしたら維持できるのか、を考えることが公共空間を問うこと、すなわちこの本の中心的な問いかけだと思います。
公共空間と私的空間の境界
また、公共空間は私的空間との関係でも語られ、その2つの関係が適切に維持されるような境界のあり方が問われます。
この境界の区別する働きが強くなると、私的空間は分断され、相互行為によってみたされる「あいだ」、すなわち公共空間が失われます。この状態の私的空間をアーレントは「真に人間的な生活にとって本質的な事柄が奪われる事を意味する。」と言います。
逆に、連結する働きが優勢になり、公共空間と私的空間との差異が消え去ると、資産化された私的空間が、いまだ資産化されていない空間を公私問わず併合しながら膨張し、やがて公共空間を食いつぶすことになります。
公共空間と私的空間の境界の区別する働きと連結する働きのバランスが、どちらに崩れても公共空間は維持できなくなるので、この境界をどうバランスよく維持できるか、が問われることになります。
疎遠化と一体化、開けた閉域へ
アーレントの問いかけをもとに論が進むわけですが、アーレントの時代と現在(2007年)とでは公共空間は異なる問題に直面していると言います。
平等の名のもと、管理行政機構によって画一化が進められた時代では、それによって自然発生的な相互行為が排除されることが問題とされ、画一化に抵抗するのが公共空間維持への実践とみなされました。
そこでは平等から自由への価値の転換が求められ、多様性・差異・民主主義と言ったことが唱われることになります。
しかし、この民主主義を求めた「自由」は、やがて資本主義的・経済的な「自由」を求めるネオリベラリズムへと横滑りし、公的なもの、すなわち国家や民主主義的な公共空間の解体を求めるようになります。
公共空間を取り戻すために平等からの転換を目指した自由が、いつしか公共空間を脅かす自由へ変容し、こうして、公共空間は新たな危機に直面することになったのです。
ネオリベラリズムもしくはグローバリズムにおいては自由は求めるものではなく、課されるものになり、公共空間を奪われた開かれた世界では、互いの間に生じた摩擦を緩和することが出来なくなります。
そして、人々は無摩擦空間をどこまでも求め、互いに疎遠になっていく(疎遠化)と同時に、身近な他者に一致状態を求めるようになります(一体化)。
また、テレビやインターネットなどのメディアは、公共空間が存在するならばそれを補完する武器になりえます。しかし、公共空間を欠いた状態では、気分や感情といった水準の公共的情動とも呼べるものによって、疎遠化と一体化を増幅するように作用します。
そこでの一体化は、単なる閉域においてではなく、メディアによって生まれた開けた閉域とでも呼べる領域において進行するのです。
こうして、資本主義が要請する自由が、政治的な討議を行なう公共空間を奪い、人々は代りに出来た閉域へと引きこもるのです。
現代のポピュリズム(極右的な排外主義、スポーツ選手やテレビタレントへの熱狂)、ないしは偏狭なナショナリズムの勃興は、この公共的情動を土台とする。その限りでは、全盛期の総動員型全体主義の土台となった世論の規格化=思想統制と区別しておく必要がある。拘束の内部において画一化し、逸脱を許さないのが全体主義だが、現代の情動の一致状態は、むしろ、画一性とは対極の、差異性、多様性が、どういうわけか不和のない均質的な一なるものへと収斂していく過程にあるものと考えられるのではないか。そしてこの一体化にともなって公共空間が解体していくのではないか。
疎遠化と一体化。公共空間の解体を論じる際には、相反する二つの過程の同時進行を問題化せねばならない。(p.34-35)
序章を読んで
以上、自分なりに序章の概要をまとめてみましたが、そこで頭に浮かんだことも記しておきます。
相互行為に満たされた空間をイメージ出来るかどうかが一つの肝になるように思いますが、この「あいだ」を満たすものはリアリティや密度感・充足感というようなイメージでしょうか。
これは、私が建築・空間に求めるイメージとも近い気がします。
建築に対しては、相互行為の相手は人でもモノでもよく、文化や歴史といった無形のものも含めて考えています。その相互行為のことを出会うという言葉に変えてまとめたのが出会う建築です。(■オノケン【太田則宏建築事務所】 » Deliciousness / Encounters)
ギブソンの生態学に相互行為を適用することで人間を取り巻く特殊な環境まで拡張したのがリードの生態心理学だと理解しているのですが、ここでの公共空間の議論と生態心理学とは重なる部分が多いかも知れません。(■オノケン【太田則宏建築事務所】 » B187 『アフォーダンスの心理学―生態心理学への道』)
そう考えると、相互行為に満たされるというのは、生態学的な知覚の欲求、生きていくための欲求が満たされることで、リアリティや密度感・充足感と結びつくのは自然なことのように思われます。
また、境界のバランスの問題も建築の自立性(建築がそれを体験する人と一体化せずに関係を結べること)との重なりを感じました。(■オノケン【太田則宏建築事務所】 » 建築の自立について)
こういう重なりは、この本での議論が一般的な「何かが失われつつあるのではないか」という関心とは別に、建築に対する視点も拡げてくれるのではないか、という期待を抱かせてくれます。
また、公共的情動に関しては炎上や社会的リンチ、新国立競技場のザハ外し事件や豊洲市場の茶番等々、思い当たるものはいくらでも挙げられそうですが、この本が書かれたのが2007年8月、twitterの日本語版スタートが2008年4月なので、この本が書かれた後にメディア、特にSNSによって公共空間のあり方がさらに変容している可能性は考えておいた方が良いかも知れません。
個人的な感覚としては、twitterでは個人が複数のクラスタ・分人的に振る舞えた時期があり、公共空間として相互行為に満たされた瞬間があったように感じますが、Facebookでは分人的振る舞いが再び個人に統合されたため、疎遠化と一体化の力が働き、公共空間としての機能は弱まっているように思います。なので、どうすればFacebookの公共空間的機能を強められるか、と言った問いの立て方はあり得るかと思います。
さて、まだ序章。問いかけがあっただけなので、これからどう展開されるのか。
第一章 境界と分離
序章では「公共空間とは何か。」「公共空間と私的空間の境界」「疎遠化と一体化、開けた閉域へ」という視点の投げかけがありました。
そこから第一章では「境界と分離」について。
ジンメルからセネット、個人から共同体へ
ジンメルは都市における分離の問題に対し、個が個を保ちながら孤立に陥ることなく生活するには、個人と群衆との間に距離を設けること(もしくは投げやり)が必要とした。
一方、セネットは都市の問題を、構成要素である共同体の問題とし、共同体の間に交渉のための場が必要とした。
セネットにおいて、都市の問題が、個人の距離の問題ではなく、共同体の空間の問題だと捉えられるが、それらの境界が、共同体が純化(境界からの撤退。疎遠化と一体化。拒絶と否定)に向かう傾向に対抗するような公共空間となるには、どの様な条件があるか、が問われる。
アレグザンダーとルフェーブル、分断と隙間
公共空間になりうる分離された空間のあいだの捉え方には二つの見方がある。
一つはあいだを、部分相互の関係を分断するもの、と捉える見方で、これが公共空間となるには、部分相互の交渉のために空間となる必要がある、と見る(分断)。
もう一つはあいだを、取り残された余地、と捉える見方で、これが公共空間となるには、内部ならざる空間を開くための余白となる必要がある、と見る(隙間)。
ここで、アレグザンダーとルフェーブルが比較される。
アレグザンダーはあいだを有限な集合の中の部分の分断として捉える(静態的)。そこで、あいだが部分相互の交渉のために空間となるには、重合(オーバーラップ)、共通項を重ね合わせることが有効とする。
それに対し、ルフェーブルは、分離した集合の間には、交流欠如の問題だけではなく、政治的な問題があるとする。集団がそもそも他の集団と分離することによって成立しているとすれば重合の有効性は限られる。
分離は政治経済的な作用の帰結であり、心的なものというより資本主義体制下での生活空間に特有の客観的性質である。
資本主義のもと、空間の商品化(工業化された空間論理、交換の論理、商品世界の論理)が進み、等価交換の領域に包括されることによる特殊性・地域性の消去すなわち「場所の均等化」の作用と、空間を剰余価値の源泉とみなし富や階級、民族や宗教の違いに応じた序列を生み出す「階層序列化=不均等化」の作用という、相反する二つの作用によって分離が生み出されるのである。(例えば、郊外は、同質性を求めて集まるところというよりは、集まりと出会いの空間から引き離し、参加の機会を奪っておくために作り出された隔離のための居住地と言える。)
さらには、分断は交流を不平等なものにし、参加者を限定していく。
ここで、分離に対して重合の施策は、有効性が限られるばかりでなくこの構造を隠蔽してしまうために適切ではない。これに対し、ルフェーブルは分離の形態ではなくプロセス・はたらきを問題視すべきであり、計画化された秩序の裂け目こそが、支配的な空間秩序に変わる空間形成の拠点と成り得るとする。
限定ではなく途上、静態的ではなく現動態的・潜勢的である空間、「他なる空間」がさまざまな事物や人を集め出会わせていく力の中心的なものと成り得る。
境界は、重なり合いのための余白ではなく、それ自体で集め、出会わせていく作用を備えた空間が生成していくための隙間である。分離は現に支配的な形態でもあるかもしれないが、これに対抗していくためには、隙間としての境界的な空間が、中心性としての空間へと生成していくことを要するだろう。それもただ一つだけでなく、無数の隙間が。(p.79)
この生成の過程は支配的な秩序に対し劣勢であるが、ルフェーブルは分離とは別の空間の出現拠点はここ以外ないと確信する。その確信がどこから来るのかは次章以降で。
第一章を読んで
ようやく第一章。(一度読んだにもかかわらず、全く先が読めない(笑)
ここまで読んで、前回書いた「分人的振る舞いが再び個人に統合されたため、疎遠化と一体化の力が働」いている状況が再度頭に浮かびました。
SNS等によってやんわりと可視化される境界と分離の構造。
それに対して個人としてはどういうスタンスをとるべきか。
実践を通じて、分離の構造の裂け目を動かしはじめている方、さらに、そこで新しく生まれた空間が結局分離の構造へと回収される、ということを避けるための振る舞いを編み出し始めている方、の顔も何人か頭に浮かびます。
ぽこぽこシステムじゃないけど、動いているということ、はたらきそのものが重要なのは間違いなさそうな気がします。
第二章 政治空間論ー均質化と差異化
前章の内容と重なりながら、ルフェーブルの政治空間論について掘り下げられます。
均質空間と差異空間 中心性と運動性
ルフェーブルは政治について、権力などの外在的なものではなく、空間そのものがどのように政治的であるか、を問う。
空間は、差異的なもの及びそのための隙間が除去されて均質的になることによって政治的になるが、それらの空間は固定的な枠ではなく、流動的で運動性を有するものとして捉えられる。
この均質化に対する実践は現実の空間が分離され、均質化されていく過程に即しながら、その中の隙間を捉えることで可能となる。その実践は新たな差異空間の生産へと繋がりうるものである。
差異空間と均質空間の間の運動と同じく、中心性の概念も変容する。中心性はさまざまな要素を集積し出会わせていく作用から、異物を除去し全体化する作用へと変容していくが、またその空間の中から集まりと出会いの作用へと中心性を変容するような隙間が見出される、というように揺れ動く。
この中心性のあり方こそが空間の質を決定する。ゆえに、均質化に対抗するには中心性の全体化作用に対抗する必要があるが、それらは現実の空間の変容過程に即してみいだされるものである。(ルフェーブルはその実践のアイデアとして脱中心化と転用を挙げている。)(逆に空間の質が中心性のあり方に関与するというような相互関係でもあるように思う。)
空間の均質化が中心性が全体化へと変容した結果だとすると、均質化に対する実践はその変容にあらがい、差異空間を現させるような集まりと出会いの中心性へと導くことで可能となる。
第二章を読んで
めちゃめちゃざっくりまとめましたが、前回
ぽこぽこシステムじゃないけど、動いているということ、はたらきそのものが重要なのは間違いなさそうな気がします。
と書いたように、ルフェーブルは空間をオートポイエーシス的なはたらきとして捉え、理論化や実践の可能性を空間と探索的に関わる行為の中に見出しているように思います。
「相互行為に満たされた公共空間」を(これもオートポイエーシス的に)維持するためには、どうすれば空間の中心性が全体化へと変容するのを阻止し新たな隙間を産出し続けられるか、を見出し続けるような視点が必要なのかもしれません。
それには、空間をはたらきの中の一地点としてイメージできるような視点と想像力、そして、そのはたらきに対して探索的に関わることができるような自在さを持つことが有効な気がします。
僕自身は、まだこの本における「政治」とは何を指すのか、をうまくイメージできていないように思います。自分なりのまとめを最後まで書いて繰り返し読み返すことでイメージできるようになればいいけど。
第三章 公共空間の政治
公共空間は脆弱な空間であるから、その喪失の過程に即した現状認識と実践が必要である。
公共空間の境界
アーレントの帝国主義時代と現代のグローバリゼーションの時代は異なるが、多くの示唆を与えてくれる。
・現れの空間…人々がともに集まるところには潜在的に存在し、相互行為によって形成され、それが途絶えると消えてしまうもの。
・境界の開放と制限
・共通世界…相互行為の土台となる具体的な場所。
・世界疎外…手の届く身近なところへの関与、および気遣いのすべてから離れたところへ退避すること。
公共空間が過度に拡張すれば、共通世界を失い、世界疎外がもたらされる。
「全体主義の起源」…国民国家が資本主義経済システムの要請に応じて外部と関わる際に、帝国主義的な膨張政策を採用した。
その膨張の暴力はやがて本国の政治体をも解体し境界を消去していく。アーレントはこの暴力の拡張を制御し、破壊から公共空間を守るために、公共空間に境界を要請した。
また、国民国家は膨張の暴力に無力で不完全な排除の政治体であるが、同時に行為者に相互行為の条件・人権を与える。
例えば、難民や亡命者のように属する政治的共同体を喪失した者には、抽象的な人権ではなく具体的な政治体を必要とする。
公共空間はあらゆる人間に、政治的行為を営む余地を与えるために開かれていなければならない。が、同時に、相互行為のための共通世界を確保するための制限、また、膨張の暴力から公共空間を守るための境界を必要とする。
境界の消去と排除壁
公共空間は観念ではなく、実質的な帰属を許容し、行為を意味あるものにする空間的な領域である。
それを暴力から守るのに必要なのが囲いとしての境界であるが、帝国主義は<帝国>へと変容し(Hardt&Negri)、内外の区別及び境界は消去されていく。
境界の消去の過程にあることを一旦受け入れた上でそれでもなお、公共空間の存立する余地は考えられるか、が問われる。
<帝国>体制下では二項対立が終焉に向かい、支配のやり方が変化し、公的なものの領域を、私有化していくと同時に、政府による監視とコントロールへと開いていく。
さらに、公共空間を確保する境界が消去された後、私有化された空間を保護するための排除壁としての境界が新たに構築されていく。
危険の排除と未来の放棄
ゲーテッドコミュニティなどの私有化された空間は、異物を除去したいという動機のもとで排除壁としての境界を具現化していくように見えるが、実のところは逆に、境界によって外から切り離されることによって恐怖と排除の動機が生み出されていく。
その境界は外に閉じるだけでなく、内なる異物を排除し、均質状態を排除しようと作動し続ける。そこで排除されるのは、外部に現存する何かではなく、内なる恐怖によるよく分からない危険な何かである。危険の排除はは予防的にあらゆるものとの関わりを放棄する。
ここで放棄されるのは未来なのである。(未来は現在と不変の状態として描かれ、出来事の永続化が目的化される。そこにあるのは計画化された空間である。)
この不可避的な力に対して著者は、抵抗や再要求ではなく、それを変化を促す生成の過程として捉えた上でそこに身をさらして思考することを促す。
脆弱性(ヴァルネラビリティ)の政治
バトラーは「不確かな生」で脆弱性の縮減、すなわち安全によって失われるものの意味を考える。
脆弱性は他者との関わりが不確かで解体しかねない状態、および関わる個々人が互いに傷つけられかねない状態であることだが、実はそれは我々の生を構成する条件であり、それが安全によって失われると言う。
相互扶助と傷つけ合う可能性の両義性を共有しながら他者との関わりに置いて脆弱性を生きることが生にとって必要なのであり、そのようにして生きていかざるを得ないということこそが、脆弱性の要請する政治なのである。
バトラー「全ての他の人間への配慮と引き換えに自分自身を安全にしようとすることは、我々が自分たちの位置を定め、道をみいだしていくための重要な財産を抹消することである。」
現れの不可視化と隙間
予期不可能なものを期待できることが、アーレントの公共空間における行為が行為であるための条件であり、安全という概念と引き換えに未来を放棄した私有空間はこの条件に反する。
さらに、この私有空間では危険が除去されているだけでなく、脆弱性を示しそうな現れが不可視化されコントロールされている。そこで阻止されているのは、耐え難い何かを知覚し判断していくための空間である。
現代の政治的活動は私有化された空間の外部に真実の公共空間を新たに創出するというよりは、支配的である現れ方の秩序に働きかけその変容を促すこと。身近なところにある、均質化の過程とそれが及ばないところの隙間に気付き、立ち止まって考えることである。
第三章を読んで
ここでもいくつかのことが頭に浮かびました。
自由を求める社会が逆に管理社会を要請する。 管理と言っても、大きな権力が大衆をコントロールするような「統制管理社会」ではなくもっと巧妙な「自由管理社会」と呼ばれるものだそう。(鹿児島の建築設計事務所 オノケン│太田則宏建築事務所 » B065 『ポストモダンの思想的根拠 -9・11と管理社会』)
見てみるとだいぶ前の本ですが、『公共空間の政治理論』の2年前でしたね。捉えどころのない時代をどう生きるか。時代による共通の問題意識が合ったのかもしれません。(今はもっと露骨な形に姿を変えているように思いますが。)
予測誤差を、痛みとか、焦りとか、ネガテイブな意味を付与する意味関連の中に配置するのか、それとも、それに対してある種の遊びの契機、あるいは、快楽を伴う創造性の契機としての意味を付与するのかによって、可塑的変化の方向性は変わると思うのだ。(鹿児島の建築設計事務所 オノケン│太田則宏建築事務所 » B176 『知の生態学的転回2 技術: 身体を取り囲む人工環境』)
熊谷氏の予測誤差を遊びの文脈で捉えることで可能性に変えていこうという姿勢は、本書での「この不可避的な力に対して、抵抗や再要求ではなく、それを変化を促す生成の過程として捉えた上でそこに身をさらして思考することを促す」姿勢に重なります。
そのようにして現実の中から何かをみいだしていこうというのが、本書の結論でもあったように思います。
個人的には脆弱性をどう生きるか、というのが今の課題のように思いました。
歳を重ねるにつけて、脆弱であることよりも安全である方を選ぶ傾向が強くなってきているように感じるのですが、それは、自分の生と未来を少しづつ手放してしまっているのかもしれません。
(著者の最近のものも一度読んでみよう。)
結論
最後にメモ的に終章から。
公共空間の存立条件
・必要なのは公共空間の存立条件が何であるかを示すこと、それも現実の只中において示すこと。
・現実には主要な実践とは異なる潜在している対抗実践との抗争状態であること。
・支配的な実践は人間にとって不可欠の条件を拒否して存続しようとしているが、その条件は抹消できないものであること。
・それゆえ、目的に無理があり永続は困難である。公共空間を実在のものとしていく実践はあながち無理ではない。
公共空間はどのようなものか
・ネオリベラリズムの均質空間と抗争的な関係にあるもの。
・耐え難いものの現れとしての行為とそれが隙間に創出するやりとりの空間をどれだけささいで脆弱的なものであっても支えていこうとすることが必要。来るべき公共空間の創出の試みはこれらのささいな空間の根底にある共有のものをみいだそうとするところからはじまる。