珪藻土試し塗り

うちで定番化しているDIY用の珪藻土ローラー塗り。
実施した季節によっては、ボード継ぎ目のクラックが入ることがあったため、新しい下地材の検討。
使い勝手とコストのバランスが良ければ採用したいと思っています。
試し塗りをした感じだと、塗料のノリが良いので塗りやすそうですし、継ぎ目を丁寧に塗れば一回塗でもいけなくはなさそうです。
今回は新しい色も試してみようかと思っています。

うちで定番化しているDIY用の珪藻土ローラー塗り。
実施した季節によっては、ボード継ぎ目のクラックが入ることがあったため、新しい下地材の検討。
使い勝手とコストのバランスが良ければ採用したいと思っています。
試し塗りをした感じだと、塗料のノリが良いので塗りやすそうですし、継ぎ目を丁寧に塗れば一回塗でもいけなくはなさそうです。
今回は新しい色も試してみようかと思っています。

今日は桜ヶ丘の家の建て方でした。
階高は低めに設定することが多いのですが、今回は途中収納スペースを挟み込んだりして1階の階高をいつもより高めに設定しています。
ですので、1階が組み上がってきた時のプローポーションがとても新鮮でした。
内部が仕上がってきた時にどういう感じになるか、楽しみです。

上棟の儀。今だけの風景。ここで一杯やりたい。


KDP主催で、昨日、今日と建築家の酒井一徳さんと手塚貴晴さんの講演会があったのですが、県内の建築家の話を聞くのも、著名な建築家の話を聞くのも、どちらも貴重な機会だと思い参加してきました。
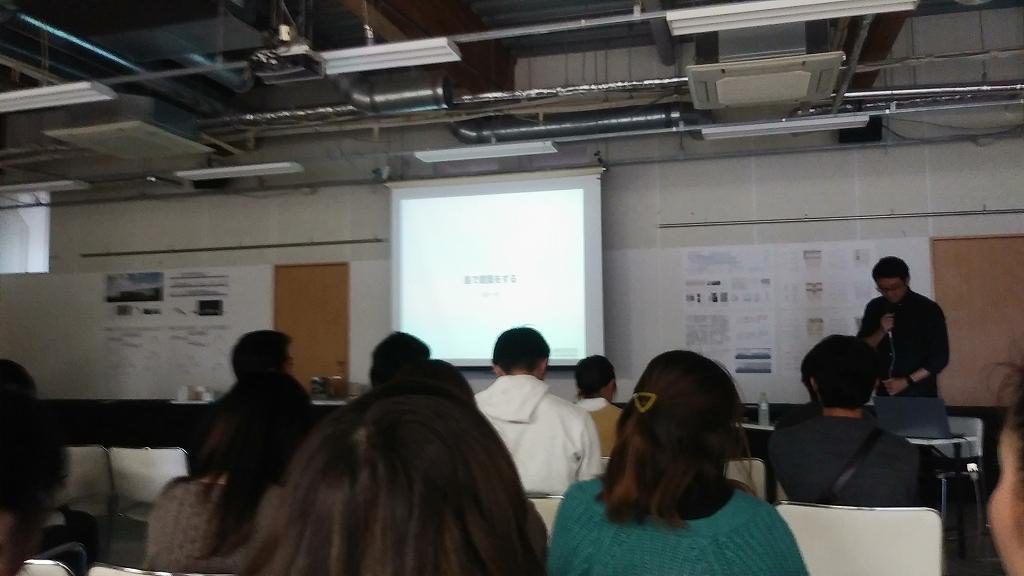
酒井さんの話は遠くの話のようで、身近な話でもあり、奄美大島という場所を拠点に奮闘を続けられている姿にたくさんの刺激を頂きました。
また、手塚さんの話はそこにいる人達が、そこにいることを心底楽しんでいる様子が伝わってきて、あらためて建築の可能性に触れられた気がしました。
思い返してみると、方法は異なるかも知れませんが、酒井さんも、手塚さんも、どちらも外というものを信頼し、大切にされているように感じました。
酒井さんは、中庭やハイサイドライト、トップライトなどを用いることと、視線などをコントロールすることを併用しながら、外へとつながる豊かな場所を生み出すのが上手く、体験として外の感覚を持たれているんだろうな、と思いました。
手塚さんは、そもそも内だ外だと言ってるのがナンセンスに思えるくらい、そこにいる人(特に子どもたち)が内も外も変わらず楽しんで使っていて、人間本来の姿を見せられたように思いました。建築よりも先にそこにいる人達がいきいきとしていることに感動させられました。
そういえば、と、自分も、昔から屋上という場所が好きだったり、例えば20畳のLDKをつくるよりは10畳のLDK+10畳のテラスなどをつくる方が気持ちが良いんじゃないか、と思っていたり、外に対する強い憧れを持っていたことを思い出しました。
予算や敷地の関係などで、実務の中では思い切ったことがあまりできていないのですが、こういう外への憧れは時々自分の中に浮かんできます。
手塚さんのスライドに出てくる子どもたちをみると、やっぱり、建築の豊かさって外の豊かさによる部分もかなり大きいんじゃないか、という気がしてきます。
(内部の面積を一般的な予算で可能な面積の3分の2以下にしてもいいので、その分豊かな外をつくりたい、という奇特な方はいらっしゃいませんかー)
また、ニコ設計室の建物を見てすごく感じたのですが、よく言われるマチに開く、というのは、オープンさ・透明さというよりは、外をどう使い倒しているか、が重要なのではないか。建物の内部に籠もり切っていない、という姿勢の表れこそ重要なのではないか、という気がします。
酒井さんの一部の建物のように、たとえ一見、外部からの視線をシャットアウトしているような屋外空間だとしても、そこに、人に楽しく使われている外がある、というのが分かれば、僕はすごく親しみを感じてしまいますし、それも一つのマチへの開き方だと思います。
さて、今後日本も大断熱時代に突入していくと思いますし、それはとても重要なことだと思います。
一方で、手塚さんの人間は本来、雑多なもの(音・光・温度・細菌等々)に囲まれていることでバランスが保たれているという話は体感的に共感できましたし、個人的にも大切にしたいと思うことと重なります。
しかし、根本的な姿勢の部分で、手塚さんの言われたことと、建物の外皮を強化して内部を外の環境から切り離すこととは、少なからず相反する部分があるように思います。
これに関しては自分の中でも揺れ動く部分があって、「建築全体の豊かさが上がるのであれば断熱性能は多少犠牲になってもいい、という考えは言い訳なのではないか」とか「断熱を言い訳にして本来の豊かさを犠牲にすることは人間にとって(特にこどもたちにとって)本当に良いのか」と、いろいろ考えてしまします。
どちらも満たせるのが一番に違いないのですが、この大断熱時代において、豊かな建築のあり方とは何か、もしくは豊かな外のあり方とは何か、しっかり考えて答えを見つけていく必要があると改めて思わされました。
実は、これに関してもニコ設計室の建物がヒントになると思っていて、彼らの建物の多くは内部と同じように外部も人が使う大切な場として、マチと建物の間に挟み込まれるようにつくられていて、そういう建物は内部を高断熱な仕様としても、外があるおかげで息苦しく感じる建物にはならないように思います。また、うまくすれば外部が内部の温熱環境をコントロールするような役割を果たすことができそうです。
もしくは内部空間を温熱環境の異なる入れ子状の構成にすることで、外部との繋がり方をの度合いをコントロールすることもできるかもしれません。
まー、いずれにしても、一定の予算の中でどう実現するかというのが課題にはなってくるのですが・・・。
(もう一度。内部の面積を一般的な予算で可能な面積の半分以下にしてもいいので、その分豊かな外をつくりたい、という奇特な方はいらっしゃいませんかー)
※タイトルは象設計集団の『空間に恋して LOVE WITH LOCUS 象設計集団のいろはカルタ』のもじりです。そういえば象設計集団の外部は大好きです。
このブログでは20代の頃から考えてきたことをいろいろと書き綴ってきているけれども、書いていることの根っこにあるものは昔からほとんど変わっていない。
子どもの頃や若い頃に感じたことの先には何があるのか、それを知りたいというのが一番の原動力で、主に何かを見たり、読んだりした時に感じたことを起点に自分の中の言葉を探そうとしてきた。
そして、ふと、今の自分にはどんな言葉が残ってるのだろう、という思いが湧いてきた。
昔のようにいろいろな言葉が次々と押し出てはこない。
しばらく考えて、なんとなく頭に浮かんだのは『詩を編むように、建築をつくりたい』という言葉。
これは、ふと浮かんできただけで、うまく説明できないけれども、これまで考えてきたあれやこれや、いろんなことが詰め込まれていそうな気がする。
現実的な経験を積んでくると、考えるときのモードが経験に支配されて、昔のような瑞々しさを失ってやしないかと不安になることがある。
だけど、この言葉は思考のモードを、経験と瑞々しさを合わせたようなものに整えてくれそうな予感がある。考えるときの姿勢を正してくれるというか。
実践以外の場でどんなにいろいろなことを考えても、そのままではなかなか建築そのものには持っていけない・届かない、というのがこれまでの実感である。
届けようとすれば、それを意識的に具体的な方法論に変換しインストールするか、実践に対する姿勢が無意識的に影響を受けていくのを待つか、のどちらかしかないように思う。
あくまで予感にすぎないので上手くいくかは分からないけれども、この言葉は後者に対して作用してくれそうな気がする。
少し待ってみようと思う。
不動産のお客様からご依頼があり、吹上の既存住宅の調査に行ってきました。
お客さんによると、内部の壁に一か所大きなひび割れがあり、家が傾く等問題がないか心配なので、ホームインスペクションをお願いしたい、とのこと。
宅建業法で位置付けられている「既存住宅状況調査」を行うことも出来ますが、この調査は状況をざっくり確認し、それを客観的な物件情報の一つとすることには意味があっても、それだけでは、具体的にその建物がどういう状況で、どのような対処が必要か、またどのような性能を充たしているか、といった個別の疑問には答えてくれません。
今回は、売主側からの依頼ではなく、買主側の疑問に答えることが目的なので、公的に位置付けられている「既存住宅状況調査」ではなく、建築士の視点からの個別調査というかたちで行うことを提案しました。
問題のひび割れ箇所を見てみると、塗材や左官材ではなく、ビニールクロスの壁が、縦に引き裂かれる形で割れていました。外周部の壁であったことから、外部を確認したところ、外壁や基礎には特に異常は認められません。
次に、不同沈下していないか外壁下部のレベルを確認してみました。

周囲を数カ所測量したところ、数ミリの違いしかなく、測定誤差・施工誤差の範囲でほぼ水平と言って良い状況でした。
ひび割れの原因が不同沈下でないとすれば、この状況で考えられるのは、下地等の木材が乾燥収縮等することで引っ張られたのではないかということ。ひび割れ位置はちょうど950モジュールのグリッド上にあります。
小屋裏に入れば何か分かるかと思い、押し入れ等の天井を探るも点検口はなし。幸いユニットバスに点検口があったので小屋裏に潜って状況を確認してきました。
問題の場所に行くと、ちょうどその位置にある柱が大きく背割れしていました。背割れに沿って壁下地が移動しひび割れが生じたのは間違いなさそうです。

せっかくなので、構造や断熱の状況を一通り見て回り、結果を報告。
・問題のひび割れは柱の背割れによるもので、地盤や構造の問題ではないので心配はいらないこと。
・ただし、筋交いの位置や本数、金物の使用状況などの構造的な状態や断熱の状況は、当時建てられたものによくあることではあるけれども、改善の余地があり、かつ改善は可能であること。
・その状況は、現場の割と丁寧な仕事の感じからして悪意ではなく知識不足によるもので、それほど不安にならなくても大丈夫であろうこと。
などをお伝えしました。
今後の判断材料に使ってもらえればと思います。
住まいと土地のコパン+オノケンではこのような調査も行っています。(費用は内容によります。)

↑今回、やむなく一番下のちびを連れて行ったのですが、後で真似をしていました。
よく見てるなー
 宇野 友明 (著)
宇野 友明 (著)
幻冬舎 (2019/11/26)
twitterで知り合った友人が、この本を読んだ感想として「何となくオノケンさんと話をしている、あるいは話を聞かせて貰ってるような、そんな感じだった。」と書かれていたのを見て興味を持った。
最初は、自分と同じようなものであればむしろ買って読むまでもないかな、と思ったのだけど、その友人は、と同時に何かしら反発心のようなものもあったそうなので、なおさら読まねばいけない気がした。
著者は、設計者として独立した後、設計と施工が分離した状態に疑問と限界を感じ、自ら施工も請け負う決断をしながら、何よりもつくるということそれ自体を大切をしている。
建築の精度も経験の深さも全く敵わないけれども、求めているものはやはり自分と近いものを感じた。
それを実践されていることに羨望の念を抱くことはあっても、大きな反発心を感じることはなかったように思う(反発心を感じられなかった自分には少し残念な気持ちもある)。
しかし、同時に自分と異なる部分も感じる。
どこに、その違いを感じるのだろうかと考えて気づいたのは、著者の文章は断定的な物言いが多いけれども、自分はどうしても「~と思う。」「~ではないだろうか。」といった曖昧な表現で終ることが多い、ということだ。
それは、自分の文章、というより自分の行動に対する覚悟の違いであることは間違いない。自分はそれほどの強さを持てていない。
だけども、それだけではないような気がする。
思えば、自分も学生時代、当時の関西の建築学生の例にもれず、安藤忠雄に傾倒している時期があった。その覚悟に満ちた凛とした姿勢の建築に大きな魅力を感じた。
しかし、大学を出てからは、それとは違う、もしくは対局にあるような建築の魅力というものもあるのではないか、という気持ちが芽生えつつ、安藤忠雄の建築のような魅力も捨てられないという迷いの中を彷徨うことになる。
それは、現在に至るまで続いており、このブログは、その迷いの先にあるものを探し続けてきた記録でもある。
今のところ、そのどちらでもあり、どちらでもないような、建築の在り方を求め続けるプロセスの中にその答えがるのではないか、と思い至っており、それが曖昧な表現につながっているように思う。
言い換えると、おそらくモノローグではなくダイアローグによって建築をつくりたいのだ。
著者は、自分の中の声に、職人の手の声に、素材の声に耳を澄ませ、偶然もしくは天の声に身を委ねており、決して独りでつくっているわけではない。しかし、その声を限定し削ぎ落としていくことによって強さを獲得している、という点でモノローグ的であると思う。
しかし、そうではなく、なるべく多くの声との対話を繰り返すことで建築に強さを与えるようなダイアローグ的なつくりかたもあるのでは、と思っている。
それは、著者や安藤忠雄の建築を否定しているのでは決してない。
そうではなく、彼らがそういう風にしかつくれないように、自分にもこうしかできない、というつくりかたがあるのだと思うし、今、さんざん迷いながらもたどり着いているものは、それが今の自分の姿なのだと思うのだ。(それを受け入れてよいのでは、もしくは受け入れるしかないのでは、と思えるようになったのは最近のことだけれども。)
さて、最初に書いた友人の抱いた反発心について、自分は同じようなものを直接的には感じることは出来なかったけれども、設計者の仕事の意義や役割について人一倍責任感の強い(と思う)氏のことなので、思うことは分かる気がする。
著者が信頼できる職人と出会い、その職人が良い仕事ができるように準備することをその職務としているように、設計者も信頼できる施工者と出会い、彼らが良い仕事ができることをその職務とすることはできると思うし、設計と施工を統合することに意義や可能性があるのと同様に、設計者であることに専念することの意義や可能性もまた存在すると思う。
いずれにせよ、良い建築をつくるためにやるべきは、自分の仕事に責任と誇りを持っているプロと出会い、彼らが良い仕事ができるような舞台を整えることである。
そして、そのどちらも困難で大変な大仕事には違いないと思う。
![]()
このサイトの左下にあるコピーライト(©2002 onoken )の©の文字のところが、こっそりランダムボタンになっていて、どこかの過去記事に飛ぶようになっています。
よく自分でこのボタンを押して、このころはこんなこと書いてたんだな、と思い出したりするのですが、その時思ったことを時々ここに書いてみようかと思います。( デザインのたねの続きの感じで。)
今回はこれに飛びました。
オノケン│太田則宏建築事務所 » B134『くうねるところにすむところ06,08,14,16,21』
このシリーズ、最後に書いてある「発刊のことば」がすごく好きなのです。
環境が人を育みます。家が人を成長させます。家は父でもあり、母でもありました。家は固有な地域文化とともに、人々の暮らしを支えてきました。かつて、家族の絆や暮らしの技術が家を通して形成され、家文化が確かなものとして水脈のように流れていました。
いま、家文化はすっかり枯れかかり、家自体の存在感も小さくなり、人々の家に対する信頼感も薄らぎ、急速に家は力を失いつつあります。家に守られる、家を守る、家とともに生きるという一体となった感覚が、極端に衰退しています。
(中略)家の確かさと豊かさと力強さを取り戻すため、建築家が家の再生に取り組む必要があります。
その第一歩として大切なことは、まず建築家が、子どもの目線で家について伝えることです。本書は、子どもたちが家に向き合うための建築家、そしてアーティスト、作家などによる家のシリーズです。(『発刊のことば』より)
建物にも、オフィスや商店、駅や学校など様々なものがありますが、家というのはその中でも特別なもので、これほど人の生活と直接寄り添いあえるものは、なかなかないと思います。
だからこそ家は確かで、豊かで、力強いものであって欲しい。(と同時に、時に不確かで、控えめで、弱々しい部分もあわせ持って欲しいとも思うのですが。)
いやいや、まちもみんなの家みたいなものだと考えたら、オフィスや商店、駅や学校だって、人の生活と直接寄り添いあえるようなものの方が良いに違いない、と思いますが、それでもそれはみんなのもの。
家はやっぱりその人にとっての特別なものだと思いますし、自分が関わった家がそうであってくれたらいいなと思います。
 高橋 寿太郎 (著)
高橋 寿太郎 (著)
学芸出版社 (2015/4/25)
同じ著者が書かれた、『建築と経営のあいだ』を購入する際に前から気にはなっていたこの本も合わせて購入。
こちらの方が書きやすそうなので先に書いておきたいと思います。
建築と不動産のあいだには価値がある。誰にとっての価値かといえば、クライアントとなる建主の価値。
逆に言うと、建築と不動産、それぞれの業務が別々に無関係に行われ、その間に大きな壁がある現状は、クライアントにとっての不利益があり、実際に困る場面があるということです。
例えば、先日書いた記事(『家づくりは生活の優先順位を決めていくこと(お金について)』)のように、土地の購入前に相談して頂いたおかげで、設計者としての視点からアドバイスできた、ということも多々あります。
ですが、この本に書かれているあいだにあるものには、個別にはその存在に気づいていながら、なかなか手が出せなかったことも多いです。
また、それらが一つのまとまり・流れの中に配置されたことで、その必要性をより強く感じさせられました。
この本で大切なのは、提供するものが、(例えば家づくりの場合)家づくりを検討し始めてからの全てのプロセス、フロー全体を通してサポートを受けられるというワンストップサービスであるということにあるように思います。
ここに頼めばそれで大丈夫、という状態をつくることで初めて、お客さんは家づくりに関する不安からようやく開放されます。
そういう意味では、全体を俯瞰して、どういうサービスがあればお客さんが安心して頼めるようになるかを考え埋めていく必要があります。
また、そのサービスは、建築と不動産のあいだにある、融資や税などを含めたファイナンスや手続きのサポートなどだけでなく、建築や不動産それぞれの業務に含まれているもの(例えば建築の構造や断熱性能、耐久性等の基本性能を適切に設定することや、イニシャルコストとランニングコストによるコストプランニング、その人に合わせた価値提供など)においても多くの要素がありますし、それらの重要性は増すばかりです。
幸い、妻が不動産業(住まいと土地のコパン)をやっており、ファイナンシャルプランナーの資格も持っています。
実務的なフローを具体的に詰めていけば、すぐにでも提供可能なことは多そうです。
近いうちにそれらを一つのパッケージとして示したいと思います。
そして、その上でより魅力的なものがつくれるようにしていきたいです。

桜ヶ丘の家、足場解体。全体が見えるようになって来ました。
この瞬間はいつもわくわくすると同時にドキドキします。

リノベーション協議会が実施しているリノベーションオブザイヤー2019で、鹿児島から株式会社大城が総合グランプリを、株式会社プラスディー設計室が地域資源リノベーション賞を受賞し、その報告会があったので参加してきました。
AWARDED WORKS 受賞作品一覧 | リノベーション・オブ・ザ・イヤー2019 | リノベーション協議会
総合グランプリを受賞された大城さんは、断熱化の遅れている鹿児島で、その中でも特に断熱が軽視されている賃貸で、実際にHEAT20G2レベルまで断熱化した部屋と、断熱化を行わなかった部屋との違いを比較実証されたのですが、その向かうべき未来への本質的な取り組みとメッセージが評価されたようです。
(詳しくは ■鹿児島断熱賃貸〜エコリノベ実証実験プロジェクト〜|リノベーション・オブ・ザ・イヤー2019|リノベーション協議会)
また、大城さんの熱い、断熱に関する解説はとても分かりやすく、自分自身理論的に誤ったイメージを持っている部分があることに気付かされたり、とても勉強になりました。
断熱に関してはもはや分からない・できないでは済まないものになっています。それについても、一度要点や考えをまとめてみたいと思っています。
「設計事務所に頼むと高くつくのでは。」という疑問を耳にすることがよくあります。
これに対しては、全く違うとも言えますし、その通り、とも言えます。
どういうことかと言うと、メーカーなどの商品住宅は、ある程度決まった仕様・グレードの中から予算にあったものを選ぶことになりますが、多くの設計事務所の場合では、特にこうしなければいけない、という縛りはありません。全てにおいて、限りないあらゆる選択肢の中から、予算に合わせた組み合わせを考えていく、という作業を積み重ねていくことになります。
ただ、初めて経験する家づくりで、無限とも思える組み合わせを決めていける方はほとんどいないと思います。
そこで、設計事務所がプロの視点と経験から先導しつつ、お客さんと一緒に組み合わせを考えていくことになります。(最近はお客さんも様々な情報を手軽に集めることができるようになったので、逆にそれまでなかった選択肢を教えていただくこともあります。)
とにかく安くすることだけを目的に組み合わせていけば、当然安く抑えることが出来ますし、逆に、どれもこれも高価なもので組み合わせていけば当然高くつきます。
設計事務所を訪ねてこられる方は何かしらこだわりのある方が多いので、結果として高くなる傾向があり、それが、「設計事務所に頼むと高くつく」というイメージに繋がっていることはあるかも知れませんが、基本的な姿勢としては、お客さんの予算に合わせて要望を叶えるための最適解を見つけていく、ということが設計という行為だと思っています。

いつもお客さんには、家づくりは、生活の中で自分が大切にしたいものは何か、を探しながらそれらの優先順位を見つけ決断していく作業だと説明しています。
限られた予算の中であらゆることを満たすことはできないので、必ずなにかしら優先順位を付けなければいけないのですが、それを楽しく、メリハリをつけてできれば家づくりの8割はうまくいったようなものです。
潤沢な予算があれば別ですが、ここで、優先順位を付けられず、全て同等に扱ってしまうと、予算内に抑えるためには結局はすべてにおいて求めている基準に満たない、といった魅力に乏しいものになってしまいます。
よく、動物園で人気の動物など自然界の形態を例に出すのですが、象やキリン、サイやカバ、どれも何か一つを突出させた特徴的な形をしています。それが多くの人に人気があるのは、そういう割り切りのようなものに生きていく力・躍動感のようなものを感じるからではないのかな、と思っているのですが、住宅も同様に、優先順位にメリハリを感じられるものは愛着の持てる魅力的なものになっているように思います。
職人不足や建築資材価格の上昇などにより建設費用はじわりとじわりと上がり続けています。また、決して悪いことではないですが、構造や断熱などもそれなりの性能にすることが普通になりつつあるので、基本性能を満たすための必要コストは以前にまして大きくなっています。
加えて消費税の増税などもあり、10年前にはできたことが今同じ価格ではなかなか実現しづらくなっています。
さらに、平均年収も下がりつつあることを考えると、10年前よりも、優先順位を明確につけてメリハリのある予算配分を考えることの必要性が大きくなってきていると思います。
事務所としては、比較的高年収のクライアントに絞り込めばそれほど問題にならないのかも知れませんが、やはり、いろいろな人に家づくりの楽しみを知ってもらいたいという気持ちを捨てることは難しいです。(ローコストばかりでは事務所の経営的には厳しくなるのですが・・・)
家づくりのコストには、構造や断熱などの基本性能、設備や仕上げ等のグレード、大きさや建物形状、その他様々な要素が絡んできます。その中で、例えば、断熱等の基本性能を満たすことを優先させるために、必要な部屋や面積、時には間取りの常識を問い直して、思いっきって小さな家にしてしまう、というような割り切りが必要になることは増えてくるように思います。
その時に、一見ネガティブな決断をその家の魅力へと転換するために、設計事務所の持ついろいろな引き出し・アイデアが必要になってくるのです。(と、同時に施主自信がそれを楽しむようなメンタリティも必要です。)
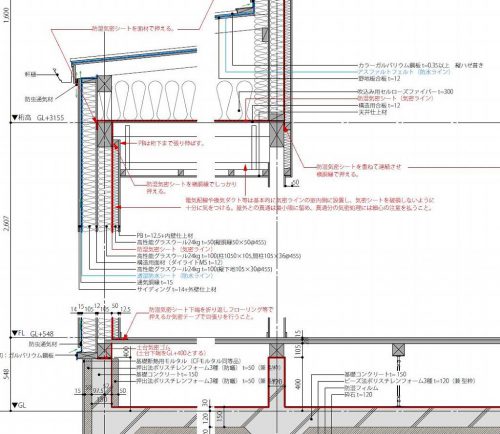
■実績ページ:HTGH ~UA0182C027の家
この家は当初、2階建てで計画していたのですが、ある日、お客さんから、高断熱・高気密の仕様(鹿児島ではなかなかないようなハイグレードな仕様)に変えたい、という連絡がありました。その際、今まで考えていた2階部分はそっくり取りやめにして1階部分の面積で構わない、と言われたのですが、とてもびっくりしました。
普通は、それまで見てきた計画案に未練が残り、何かを大きく減らす、という決断はなかなか出来ず、いろいろなところを少しづつ削っていくという選択になりがちです。
それはそれでやりようがあるかも知れませんが(現実的に無理なケースもありますが・・・)、このお客さんは、快適な熱環境を実現したい、ということの優先順位をはっきりと前に打ち出したため、それを実現できただけでなく他の部分に関しても無理のない予算を割くことが出来ました。
経験的には、コスト調整の過程でお客さんが様々な選択をしていくことになりますが、出来上がったものを見ると決して妥協の産物ではなく、はじめからその様に計画していたかのように思えることがほとんどです。コスト調整は、丁度よい塩梅を見えつけるための作業とも言えます。
また、土地から購入される場合、土地と建物の予算バランスも重要な要素になってきます。
土地と建物の総予算が3000万円で考えているのに、土地に2000万円かけてしまえば、建物にかけられる予算はかなり厳しいものになってしまいます。(実際、土地を購入後に相談に来られた方で、これに近いバランスのケースも少なくはないです。)
叶えたい生活によっても、土地と建物の予算バランスは変わってきますし、一見不利な条件の安い土地が建築的な工夫で魅力に変えられることもあるかも知れません。
可能であれば、土地を探している段階で相談に来られることをおすすめします。

■実績ページ:MKGT ~南郡元の家
この家のお客さんが相談に来られたとき、2つの敷地で迷われていました。
一つは14.3坪の土地で、もう一つは18坪の土地。後者の方の土地はいろいろな条件から前者の2倍以上の金額でした。(建ぺい率/容積率は60/200と60/160)
お客さんとしては前者のエリアのほうが馴染みがあるけれども、さすがに14.3坪は難しいだろうし、環境としては後者のほうが良いように思う、ということで悩まれていました。
総予算をお聞きして、試算してみたところ、後者では建物にかけられる金額がかなり厳しく、思い描くようなものを実現することは難しいように思われました。
そこで、なんとか建物の方を工夫すれば良いものにできると思うので、予算の上限を上げることが難しいのであれば、こちらを選んだ方が良いのでは、と小さい方の土地を推薦したところ、それを信じて頂いて、そちらで進めることになりました。
スキップフロアーを採用し、床下収納やロフトを組み合わせることで、妥協的ではないプランをまとめることができたのですが、結果的には、仕様的にもほとんど妥協せずに進めることが出来ました。お客さんにも満足して頂けたと思います。
ところで、ここまで、家造りの総予算と言う言葉が何度もでてきていますが、そもそもの予算はどうやって決まっているのでしょうか。
今までは、総予算はお客さんの方で決めて頂いて、それをもとに計画をしてきましたが、本来であれば、将来のライフプランとファイナンスプランによる具体的な数字を算出し、それをもとに決定した方が、より適切な金額を採用できますし、何よりお客さん自信の不安が取り除かれより前向きに家づくりに取り組めるはずです。
その部分は、今までなかなかアプローチできなかった部分ですが、お金に関する諸々に対しても責任を持って提案・サポートできるような体制を近いうちに準備したいと思っています。

某テナントの現場がだいぶ仕上がってきました。
本体建築の検査関係で建築工事の工期が年初の1ヶ月弱しか無くバタバタでしたが、なんとか納めて頂けそうです。
しばらく間をおいてから、サインや金物などの雑工事を行う予定ですが、こっちは余裕を持って検討できそう。

今日はプレカットの事前打ち合わせでした。
今は木造の軸組を大工さんが手刻みで加工してくることは少なくなり、ほとんどが工場での機械加工(プレカット)になっています。
設計図を元に起こしたプレカット図面を、設計者と施工者(現場監督・担当者)、プレカット会社の三者で時間をかけて入念にチェックするのですが、ここが現場監理の一つのキモであり、三者の能力が問われるところでもあります。
現場に入ってから後で慌てないように、構造強度に関することはもちろん、木の組み方、金物との取り合いや作業性、室内の仕上げ方や設備配管のルート、その他様々なことを想定しながらチェックしていきます。
自分は設計者なので、当然一通りは頭の中に入っています。毎回チェック漏れのないつもりでこの打ち合わせに臨むのですが、ここの監督さんは、それ以上に現場目線からよりきれいに納まるようなポイントをいくつも指摘・提案して下さります。事前に図面の隅々までを頭に入れて、つくる過程を綿密にシミュレーションしていなければ、できることではありません。
打ち合わせもそれだけ長丁場になりますが、おかげで安心して現場を進められ、ありがたいことです。(と言って気を抜いて相手任せになればミスのもとになりますが)
また、プレカット会社まかせの設計者や現場監督も多いと聞きます。プレカットの担当者もプロで、図面を見てかなりの配慮はしてくれていますが、それにも限度があります。それでも現場がまわっているのは考えなくてもつくれるような単純な、もしくは一般的なつくりなのか、後で現場でつじつま合わせをしているかどっちかなのでしょう。(前者には前者なりの利点がありますが。)
うちは、スキップフロアーなどの複雑な構造や、メリハリをつけるために木の組み方や寸法を攻めてたりすることが多いので、どうしても、知恵を持ち寄るこの打ち合わせは欠かすことができません。
毎回、そうやって力を合わせていただけるおかげで実現できているのだと思います。

先日VECTORWORKSの2020年版がリリースされたので、早速入れてみました。
新機能のうち、期待しているのは
・データマネージャ
・新しいウォークスルーアニメーション
・履歴ベースの3Dモデリング
・作業中のデータの可視化
など。
特にデータマネージャは昨年追加されたデータタグと組み合わせることで、かなりの効率化と整合化ができると思うのですが、少し触った感じでは、まだ思うように使えていないです。想定外の挙動もあるのでサポートにも聞きながら使いこなせるようにしたいところです。
ウォークスルーアニメーションに関しては平面的にパスを指定することで自動で階段を登ったり、360°ムービーが作成できたりと、かなり使い勝手が良くなっていそうです。これまでのバージョンはアニメーションがかなり使いづらかったのでそれほどは期待していなかったのですが、想定よりずっと良いように思いました。
新しいことをどんどん覚えていかないといけないですが、ソフトウェアでできる効率化はとことんやって、できる限り検討に時間を割けるようにしていこうと思います。

コムストアで「暮らしをつくる」をテーマに、ブルースタジオ大島さんとアカツキ建築設計二俣さんのトークセッションがあったので行ってきました。
あえて強調すると、大島さんは俯瞰した視点から、関係性を編み込みながら暮らしを編集するような外からの視点、二俣さんはものをつくる手さばきの中から暮らしを組み立てていくような内からの視点。そのバランスがとてもいい感じのトークセッションでした。
20世紀に躍起になって求めた利便性の多くは、関係性を断ち切り、生活・暮らしを切り売りしていくことと引き換えに得られたものが多く、その過程で生活がどんどん受動的なものになっていったように思います。
仮に20世紀を受動と分断の時代だとすると、21世紀はこれまで手放してきたものに光を当て、関係性を紡ぎながら再び手元に引き寄せていくような、能動と関係性の時代となっていくはずです。
そんな時代の中で暮らしをつくっていくには、関係性を編み込むための俯瞰的・編集的な視点と、関係性の拠り所となるようなものをつくる手さばき、そのどちらもがますます重要になってくるのでしょう。
(トークを聞きながら、そんなことどっかで書いたなー、と思ったら「雑木林と8つの家」に参加した時でした。スライドをアップしたのを思い出して、検索したらまだ残ってた。 https://www.slideshare.net/onokennote/320-12123035 めっちゃ懐かしいし、今考えても思いのこもった良いプロジェクトだったと思います。)

下竜尾町の家の地鎮祭でした。
今回、第一種低層住居専用地域で軒高が7mを越えていたこともあって、コンパクトな住宅でありながら、日影、北側斜線天空率、標識設置届と近隣説明、景観法の届出、崖相談、省エネ計算と全部盛りのような感じでした。
時間がかかりましたが、標識設置届の写しと確認済証を待っていよいよ着工に漕ぎ着けられそうです。
10年ぶりくらいに作る書類も多くて、いろいろ思い出しながら復習にもなりました。
着工が楽しみです。

新年明けましておめでとうございます。
旧年中は大変お世話になりました。
おかげさまで、次の12月で事務所立ち上げの展覧会を開催してから10年になります。
今年は次の10年に向けての研鑽と変革の年とすべく、また、建築・設計を通してさらに良いサービスが提供できるよう、誠心誠意向き合っていく所存でございます。
皆様のご健勝と益々のご発展を心よりお祈り申し上げるとともに、本年も変わらずご愛顧を賜わりますようよろしくお願い申し上げます。
2020年 太田則宏建築事務所 太田則宏
本書はリードによる生態学的経験科学を環境を記述するための理論と捉え、保育実践及び保育実践研究を更新していくための実践的な知として位置づけようとするものである。
私も以前、建築の設計行為を同じくリードの生態心理学とベースとした建築論としてまとめようとしたことがある。
「おいしい知覚/出会う建築 Deliciousness / Encounters」
そのため本書は大変興味深いものであったが、結論から言うと、それは「出会う建築」において、今までなかなか埋めることの出来なかった重要なパーツ(何かに「出会わせよう」とすることが逆に出会いの可能性を奪ってしまうというジレンマをどう扱うか)を埋める一つの道筋を示してくれるものであった。
また、それだけでなく、保育実践に関わる本論の多くが建築設計の場面に置き換えて読むことで、その理解を深めることができるようなものであった。
(長くなったので前提の議論をすっとばすならここから。)
デューイにとって環境とは単なる教授の手段ではなく、教師と子どもがともに経験し、自己を再構成し続けるメディアである。そのメディアは、教育的状況において常に同じ教育的効果を発揮するといったものではない。メディアとしての環境は教育的状況の中でその都度出会うものであり、多様な仕方で生活を更新する。そして、教師が教育的状況において、子どもの成長についての問いをめぐらし、その環境との一回性の出会いをどのように理解するのかという課題を背負うとき、そこには人間と教育についての根本的な問いが含まれることになるのである。(p.59)
環境との出会いは一回性のものであるから、実践の場における決断のための論理にはなれない。もしくは、環境概念は意図を実現するための手段・固定的な道具である。
環境についての議論はこんな風に捉えられてしまいがちで、それによって本来の豊かさを失ってしまうという課題を抱える。そのことは、そのまま「環境を通した保育」を実践する上での現代の保育環境研究における課題へと連続する。
それは現在、環境を捉える際にも支配的な、主観と客観の二元論に基づいた客観主義心理学的な認識論が抱える問題点でもあるのだが、ここから抜け出すために、著者は保育者-環境-子供の系において生きられた環境を記述するための方法論が必要である、とする。また、それが本書の趣旨であるように思う。
同様に、環境との出会いという概念を建築の設計やデザインの分野に持ち込もうとした場合、「アフォーダンス」という言葉の多くが環境を扱うための硬直化した「手段」として捉えられていることが多いように、近代的な計画学的思考に囚われている我々も、そこからな抜け出すのはなかなか難しい。
しかし、実際の設計行為に目を移すと、それは偶発的な出会いに満たされており、その中で日々決断を迫られながら、環境との出会いとどう向き合うかを問われ続けている。引用文をパラフレーズするならば「設計者が設計の場面において、建築と人間の生活についての問いをめぐらし、その環境との一回性の出会いをどのように理解するのかという課題を背負うとき、そこには人間と建築についての根本的な問いが含まれることになるのである。」とでもなるであろうか。
手段的・計画的な思考とは異なるやりかたで、この一回性の出会いと向き合うことができるかどうか。それによって、環境との出会いに含まれる豊かさを、建築へ引き寄せることができるかどうかが決まるのである。
その際、設計行為を設計者が建築を育てるような行為だと捉えるとするならば、設計者-環境-建築の系において生きられた環境を記述するための方法論が必要である、と言えそうである。
「環境との出会い」を記述しようとしても、客観主義心理学的に環境のみを記述するだけでは十分に捉えることが出来ない。そのような問題に対して「出会い」を捉える実践的な論理として先行していたのが現象学である。
ただし、教育学においては具体的な教育実践に向き合う必要があったことから、現象学は、現象の基礎づけへと向かうフッサール的な超越論的考察を留保し、教育現象の「記述」の方法に限定されたかたちで導入されてきたのであるが、これによって保育学にも生きられた事実を明らかにしようとする、記述のメタ理論がもたらされた。
しかし、現象学では主観による意味付与というかたちで環境を記述し考察する。このとき解明される保育環境は、空間経験の主観的側面に限定され、文化や環境そのもの特性は背景化されるという限界がある。
これに対し、レヴィナスは「意味付与」に先立ち現前する「意味作用」としての他者というものから経験を捉えようとしたが、本書ではそのレヴィナスの批判を引き受けつつ、現象学の限界を補完するものとして生態心理学の思想をもう一つのメタ理論に位置付けようとする。
それは、
本研究は経験についての形而上学を行おうとするものではなく、形而上学的に考察された「経験」や「主観性」、「記述」といったことの意味を、現実の保育実践研究のメタ理論として捉えなおし、保育環境について問いなおそうとするものである。(p.109)
この文章の保育という言葉を設計に置き換えると、そのままこの記事で書こうとしていること、もしくは「出会う建築」で書こうとしたことに重なる。
設計行為という実践の場でふるまうための方法論が欲しいのだが、本書ではそれを環境を記述するためのメタ理論に求めているのだ。そのことについてもう少し追ってみたい。
本書では現象学を否定し、代わりに生態心理学を位置づけようとするものではなく、両者を相補的なものと捉えている。両者を両輪に据えるためのメタ理論としているのがプラグマティズムである。
ジェームズによれば、プラグマティックな方法とは、「これなくしてはいつはてるとも知れないであろう形而上学上の論争を解決する一つの方法」であり、それは論争の各立場が主張する観念のそれぞれがもたらす「実際的な結果」を辿りつめてみることによって、各観念を解釈しようと試みるものである。(p.125)
要するに、ジレンマを抱える2つの考えの美味しいとこ取りをしよう、ということのように思うが、そうやって現象学と生態学的経験科学を扱おうというのが本書の意図である。(著者自身はそのうち生態学的経験科学の方に軸足を置いている)
現象学は主観による意味付与の省察によって表象的世界の記述を行う(生きられた世界の現象学的還元)。
生態学的経験科学は環境の意味作用の省察によって生きられた環境の記述を行う(環境のリアリティの探求)。
保育実践研究をひとつのコミュニケーションとして捉えると、そこには送る側と送られる側双方に経験の変容が生じることで、相互の理解が深まり、実践の理解の在り方が変化していく。保育実践研究の発展はこのようなプロセスの中に見いだされるものなのである。(p.129)
ここで、設計行為の設計者-環境-建築の系で考えた場合、保育実践研究と保育実践は批評と設計行為にあたる。ひとつの案件で建築を育てていく場面では、この批評の部分をどうプロセスの中に置くことができるかが重要なポイントになる。とくに私のようなぼっち事務所の場合、この両者のコミュニケーションは単なる独り言になってしまいうまくサイクルがまわらなくなりがちである。その時にこれらの記述のためのメタ理論が、もう一人の自分に批評者としての視点(イメージとしては人格)を与え、対話的サイクルを生むための助けとなるような気がする。
アフォーダンスは直接経験可能な実在であるが、ノエマ(付与された意味)として主体の内部に回収されるものではない。それは環境に存在し、他者と共有することが可能な実在である。(p.163)
リードは環境を共有可能なものとして捉えた。「おいしい知覚/出会う建築 Deliciousness / Encounters」でも環境の共有可能性・公共性を重要な視点の一つとして位置付けたが、本書ではその公共性をリアリティを共同的に探求していくための根拠として位置づける。
共通の実在(reality)は、その価値が実現(realize)していく中で、確証されていくのである。(p.173)
以上のように、保育を「そこにあるもの」のリアリティの共有へ向けた探求として考えてみるとき、その探求を駆動しているのは、私たちが「そこにあるもの」の意味や価値を汲みつくすことができないという事実である。(中略)しかし、「そこにあるもの」は、私たちが自由にそれに意味を付与することができる対象なのではない。経験は、その条件としての環境のアフォーダンスに支えられている。(p.175)
保育は環境の中に潜在している意味と価値、そこに含まれているリアリティをリアライズしていく過程そのものと言える。
同様に建築の設計行為もその環境の中に潜在している意味と価値、リアリティをリアライズしていく過程だと言えよう。
それを支えているのは「そこにあるもの」の意味や価値を汲みつくせないという事実であるが、これは容易に見失われてしまうものでもある。
私は建築が設計者や利用者の意識に回収されないような、自立した存在であって欲しいと思っているが、設計行為はややもすると、施主や設計者の願望をかたちに置き換えただけのものになってしまうし、どちらかと言えば「そこにあるもの」の意味や価値をできるだけ汲みつくせるものにすることを目指しがちである。そしてそのような場面では、容易に汲みつくせないような意味や価値は、ないものとされがちである。
そのプロセスには、そしてそうやってできた建築物には、もはや新しい出会いで満たされる余地は残っていないし、むしろそのような余地自体が敬遠されているようにも思う。
第Ⅲ部では、具体的なエピソードを交えながら保育という実践の中で環境の「充たされざる意味」が充たされていく過程とその意味が描かれる。
実際の保育の現場では、刻々と変わる状況の中、例えば「教育的意図を実現するか、子どもの主体性を尊重するか」というような、さまざまな二項対立的な葛藤の中で、保育者として瞬時に何らかの決断を下さなければならない、ということがよくある。
リードは、自分と異なる価値観をもつ他者、自分と異なる行動のパターンを持つ他者を理解する上で、環境の「充たされざる意味」を充たしていく過程が重要であると主張する。(中略)「充たされざる意味」とは、私たちの周囲を取り巻いているが、いまだその可能性が知覚されていない情報のことを指している。(p.187-188)
他者が環境と関わる仕方を目の当たりにした際、そこで「何か」が起こっていると感じ取ることによって、理解への道が開かれる。時に保育者は、理解できない子どもの行為に直面したり、子どもの行為の意味の解釈について葛藤を抱えることがある。(中略)それは葛藤やゆきづまりという状況に踏みとどまり、その状況を探索することで「充たされざる意味」を、共に充たし発見していくという相互理解の在り方なのだといえよう(p.189)
例えば、設計者の意図と施主の意見、家族同士の意見の相違、機能性と機能性以外の価値、など、建築の設計行為の中でそういった「どちらをとるか」というような場面はよくある。そして、保育での場面と同じように何らかの決断を下さなければならない。また、保育の場がリードの「行為促進場」としての在り方を問われるように、設計行為の継続のためには設計行為の行われる場の在り方も問われるだろう。そういった場面ではどういったことが考えられるだろうか。
本書では、それに対して、「充たされざる意味」を共に充たしていく過程、もしくは保育者の実践的行為を保育-環境-子どもの系の調整として捉えることによって二項対立を克服するような関わりの在りようが示される。
そこに明確な回答が存在するわけではないが、そこで第三の道が見いだされるような場面には保育者の「感触」を見逃さないような姿勢があるように思う
さて、ここで、設計を、建築における環境との出会いの一回性と向き合い、環境の中に潜在している意味と価値、リアリティをリアライズしていく過程として捉え、それを実践するためにプラグマティズムのメタ・メタ理論のもと、環境との出会いを記述する理論として、現象学と生態学的経験科学を位置づける。そのうち、環境のリアリティを探求するために生態学的な記述によって考察するのがエコロジカル・アプローチである。とした時、エコロジカル・アプローチとはどのようなもので、実践的な役割はどんなものだろうか。
その前に、こんがらがってしまったので、先に一度整理しておきたい。
建築において「環境との出会い」を考えるとき、次の2つの系があると想像していた。
・設計者-環境-建築の系 設計行為の実践の中で、現場状況や法的規制、施主の要望等も環境として捉え、建築を育てていこうとするような場面。保育の場面では、保育者-環境-子どもの系で保育者として実践する場面に相当すると思われる。
・環境-人の系 完成後の建築を人の環境として捉え、建築そのものが人にどう出会われるかを考えるような場面。保育では保育環境を子どもとの関係を考えながらどう考えるか、という場面に相当すると思われる。
しかし、前者は実際は建築が直接環境と出会うというのはいい難い。ここは、設計者-環境(建築)-人(与件)の系なのではないか、そう考えると道筋ができそうな気がしてきた。(建築を育てていこうというイメージで設計者-環境-建築と考えるのは環境を手段とするような見方が入り込んでしまっていたように思う。)
設計行為の実践の中では、人を含めた与件・設計条件の中で、建築という環境を発見的に調整していく(環境の中に潜在している意味と価値、リアリティをリアライズしていく)というプロセスを繰り返すことで、建築の中に自然と意味と価値が埋め込まれていく(埋め込んでいくのではない)。設計者はその中で自ら「充たされざる意味」を(共に)充たし、リアリティに出会おうとすればよい。
そうして出来上がった環境としての建築は、設計者が関わりを終えた後でも、共有可能な出会いに満ちたものになっているはずである。そこでの出会いのプロセスは別物なので、人が何にどう出会うかは分からないし、設計者がなにかに出会わせることはできない。しかし、それによって建築はおそらく豊かなものになるだろうし、設計者にそれ以上の事はできない。
そう考えるとすっきりしたし、この後で考えようとしていた、出会いのジレンマ(冒頭で書いた、何かに「出会わせよう」とすることが逆に出会いの可能性を奪ってしまうジレンマ)をどう扱えば良いか、という問いにも、意図せず応えられそうである。
完成後の建築に出会わせようとするのではなく、設計行為の中で出会おうとすればそれでよいのだ。私自身が、環境を手段とみなす視点からなかなか抜け出せなかったので、得られたのは個人的に大きい。
そして、その出会いを探求するための理論がエコロジカル・アプローチなのである。
であるとするならば、実践の中で、もしくは過去の実践を振り返りながら、「環境との出会い」を記述する方法を身につけていくことが設計の精度をより高めていくことにつながるだろう。
本書は最後こう締めくくられる。
繰り返すが、保育者は潜在する環境の「意味」や「価値」に出会わなければいけないのではない。ただ、「そこにあるもの」が発する可能性に耳を澄ませることが、子どもとともに生きるなかで、世界と新たな仕方で出会う力になるのである。(p.247-248)
そう、設計者は潜在する環境の「意味」や「価値」に出会わなければいけないのではない。ただ、「そこにあるもの」が発する可能性に耳を澄ませることが、設計を行うなかで、世界と新たな仕方で出会う力になるのである。
重複もあるが、本書の中から要点をいくつか抜き出して箇条書きでまとめてみる。
・アフォーダンスを知覚することは「そこにあるもの(things out there)」のリアリティが一つのしかたで現実化(realize)すること。(p.181)
・共通の実在(reality)は、その価値が実現(realize)していく中で確証されていく。(p.173)
・環境は、確かにそこに在るが、それは同時に汲みつくすことの出来ないものとして存在している。そのことによって環境は、子どもの経験世界と保育者の経験世界をつなぐメディアとなっている。(p.176)
・複雑な保育実践の「場」を捉えていくには、環境を独立して扱わず、系の全体性を損なわない形で人間と環境のトランザクションを記述する理論が求められる。(p.184)
・自分と異なる価値観をもつ他者、自分と異なる行動のパターンを持つ他者を理解する上で、環境の「充たされざる意味」を充たしていく過程が重要。(p.187)
・環境は、保育者が子どもの育ちへの願いを込めるメディアでありつつ、常にその意図を超越した出会いをもたらすメディアでもある。(p.202)
・「充たされざる意味」を充たすことは、環境に新たな仕方で出会い、環境の理解を更新する営み。(p.205)
・「意味」と「価値」を環境に潜在するものとして捉えることで生じるのは、保育者が「環境の未知なる側面」に注意を向けていく動きである。(p.209)
・環境の「充たされざる意味」という概念は、「意味ある何かが進行している」という状況と、コミュニケーションを通してその「何か」が確定していくプロセスを記述することを可能にする。(p.213)
・エコロジカル・アプローチにおいては、記述される経験についての省察は、主観の意味付与の過程に内生的に向かうのではなく、主体に先立つ、経験を可能にした条件としての環境の実在に向けられる。(p.227)
・エコロジカル・アプローチは二項関係ではなく、「生きられた環境」の系のなかで出会うアフォーダンスを探求しようとする。その際、保育者と子どもとが知覚しているアフォーダンスの差異が探求の手がかりになる。(p.228-229
)
・環境は記述しつくせない。「そこにあるもの」は、常に私の意味付与の権限の及ばない<他なるもの>として到来する可能性をもって潜在している。(p.230)
・エコロジカル・アプローチは再現可能性に基づく科学ではなく、公共的な議論の場を開いていく保育実践の科学。(p.230)
・出会いの条件となる環境を記述するが、「出会わせる」ことのできる環境は記述できない。環境は生成体験のメディア。(p.230)
・日常の環境は、新たな出会いを可能にする重要な資源(p.231)
・環境は探求されるものであると同時に、その出会いは実践のなかで偶然性を伴って到来する。(p.231)
・日常生活における「ありふれたもの」は生成体験のメディアになることによって、「有用性」のエコノミーに回収されることのない保育実践を生じさせる。保育者と子どもが接する環境が、「そこにある」と同時に、「出会われていない」という自体は、生活のなかで日常を超え出ていく可能性を担保し続ける。(p.235)
・「有用性」基づく思考様式に回収される日常を脱しない限り、保育実践もまた「発達」の論理に回収されることとなる。しかし、生活のなかには、日常のエコノミーを超え出ていく通路を見出すことができるはずであり、保育学にはその道を照らし出す責任がある。(p.237)
・記述した環境を対象化し、手段化することは出会いという生成体験を日常性のエコノミーへと引き戻してしまう危険を常に抱えている。子どもをしてなにかに「出会わせよう」とすることは、逆に子ども自身の出会いを妨げることになりかねない。(p.241)
・より良い保育実践の探究は、身の回りに「出会われていない環境」が存在し、「そこにあるもの」が、今自分が見ているものとは異なる「意味」や「価値」をもって経験される可能性があり得るということを「気に留める姿勢」を持つことによって可能になる。(p.244)
・メディアがメディアとして立ち現れるとき、その第1の条件となっているのは、手段としての環境への関心ではなく、そのときの保育における子どもへの関心である。そして第2の条件となるのが環境の探求である。(p.245)
・環境の可能性を気に留めておくことは、環境の意図の実現の手段にするのでもなく、環境を通した保育に無関心でいるのでもない、環境に異なる「意味」や「価値」を見出す予感を備えて実践に臨むことを示している(p.245)
余談になるが、本書を読んで先日読んだ『損傷したシステムはいかに創発・再生するか: オートポイエーシスの第五領域』と重なること、同じことを言ってるんじゃないか、と感じることが多かった。例えば次のような部分である。
「臨床の知」は、外部からの観察によるのではなく、身体を備えた主体としての自分を含めた全体を見通す洞察によってもたらされる、探求によって力動的に変化する「知」なのである。(p.83)
ギブソンが知覚を行為として捉え、それが「流れ」であり「終わらない」ものであると捉えている点に注意を向けるとき、(中略)ギブソンは知覚を、単なる意識でなく、「気づくこと」であると述べる。(p.171)
-意味ある何かが進行している-ということの知覚こそがほとんどの場合、そうした状況内に見出される記号的あるいは社会化された意味を確かめようとするいかなる試みにも先立って起こる。(p.188)
それ以外にも運動・動き・更新・生成・~し続けるといったはたらきを示す言葉や、「なにか」「感じ」「予感」といった触覚的な言葉も頻発する。加えて、手段や目的といった客観主義心理学的な思考を回避しようとすることにもオートポイエーシスとの重なりを感じるし、かなり近い現象を捉えようとしていることは間違いないと思う。
著者は、記述の問題を、保育実践研究というはたらきのなかに位置付けているし、個々の保育者が身につける臨床的な技術のイメージは河本氏の著書の臨床のイメージとかなり近いように思う。
なので、保育実践研究や、保育実践及び設計行為のはたらきの部分はオートポイエーシス・システム論によって記述しても面白そうである。
先の設計行為に当てはめるとすれば、設計の完成形を先にイメージするのではなく、設計目標のイメージを一旦括弧入れした上で、設計者-環境(建築)-人(与件)の系の中で、環境探索と批評及び環境調整のエコロジカル・アプローチ的なサイクルを「その結果として「目標」がおのずと達成される。」ように繰り返す。このエコロジカル・アプローチ的サイクルはまさしくオートポイエーシスの第5領域における「感触」「気づき」「踏み出し」といい変えられそうである。
おそらくこれらの2つを組み合わせることでよりいきいきとしたものが記述できるようになり、さらに実践的なイメージが湧くのではと思ってしまう。
昔から、アフォーダンスとオートポイエーシスは近い場面を描こうとしているのに、なぜダイナミックに組み合わされないのだろうかと疑問に思っている。
同じ場面を描くとしても、アフォーダンスは知覚者と環境及び環境の意味と価値について構造的なことの記述に向いているし、オートポイエーシスは知覚や環境の変化を含めたはたらき・システムの記述に向いているように思う。
それぞれ得意分野を活かしながらなぜ合流しないのか、不思議に思う。もしかしたら両者の間に埋められないような根本的な溝があるのかも知れないが、それこそプラグマティズムのもとに合流しても良いような気がする。
もし、著者が保育実践研究について、オートポイエーシス的な視点を加えたものを書くとするなら、読んでみたい気がするし、河本氏の著書にどういった感想を持つか聞いてみたい気がする。

千年の家の地鎮祭を執り行いました。
最初にお問い合わせを頂いてから、土地探しからじっくり検討しながら、2年以上、ようやく地鎮祭にまでこぎつけることができました。
これからの進行が楽しみです。
『色彩の手帳』は「色が苦手」「色は難しい」「色は結局好き嫌いだから」「自分には色選びのセンスがない」と一度でも感じたり、考えたことのある”全ての”人のために制作したものです。(p.1)
この本の基になった『色彩の手帳・50のヒント』が3年ほど前にtwitterのTLで評判が良くて、ずっと気になってたのだけど、遅ればせながらバージョンアップ?した本書を購入しました。
内容が具体的で納得する部分が多かったので紹介的な文章になってしまいますが、簡単に感想を書いておきたいと思います。
色に関する本は数冊持っているのですが、建築の分野でここまで実用的な本は自分の知っている中では初めてで、かなりおすすめの一冊です。
間違いなく多くの人に手にとってもらいたい一冊なのですが、
仕事をともにする方々の「何を根拠に色を選べば・決めれば良いのか」というあまりにも多くの問いに対し、自身が何か決めて終わりではなく「色選びの手がかり」や「色の選び方のヒント」をお伝えし、その成果や効果を共有する方が、もしかすると「色彩計画家」としての機能はもっと広く、そして永く活かされるのではないかと考えるようになったのです(p.1)
というように、多くの人が色に対してどう向き合ってよいか分からない(故に、無根拠に個人的な思いつきで色が決められていく)という現実がこの本が書かれることになった背景にあるようです。
そのことを考えると、個人や公共を問わず発注者となる立場の方、もしくはまちづくり等に関わる方に、より多く読んでもらいたいと思いました。
色に対する向き合い方をまずは知ることで、変えられることがたくさんあるように思います。
内容も色彩に関する基本的な理論から、具体的な事例や色彩計画へのアプローチの方法、著者自信の色彩または建築や都市に対する考え方と経験を基にした思想的な部分、その思考プロセスなど、およそ建築の色彩に興味を持った人が知りたいと思うようなことがすべて、と思えるくらいばっちり描かれています。
最初に目次に目を通すだけで早く読み進めたいとワクワクしましたし、著者自身が、色彩に関して誠実に、そして秩序立てて考えているのが伺えました。
世の中、何もかもが秩序を保つ必要はありませんが、こと色においては、何らかのルールに基づくものは心地よく感じやすい、という性質があることに、私自身は信頼を置いています。
この秩序はある程度までは理詰めで導き出すことが出来ますから、色彩的な調和の感じられる配色を考えるのにセンス云々ということはあまり関係ないのでは、と思っています。(90 集めた色を並び替える p.207)
色彩計画の流れとは、色を選ぶ・決めるためのシステム設計だと考えています。(94 色彩計画の流れ p.217)
本書のヒントから、あるいはいくつかのヒントを組み合わせてぜひ「色彩を計画」してみて下さい。(100 色彩を計画する p.229)
これらの言葉には「色彩を計画」することに対する信頼が感じられますし、「色彩計画の流れとは~」の一文は「建築計画の流れとは~」と置き換えてイメージすると、その信頼の強さとより良く選びたいという誠実さが伝わります。
(この辺になんとなく建築家に似たような性分を感じますが、本文に時々出てくる、おそらく抽象化を計りたいのであろう建築家の一言vs著者の一言も、どちらも分かるだけに興味深いです。)
自分自身、今まで無難な色使いをすることが多かったですが、もっと色を使えるようになりたい、感覚的にも使えるようになりたいし、なおかつ根拠を持って使えるようになりたい、という気持ちはだんだんと大きくなりつつあります。
なので、まずはこの本と色見本帳を片手にもっと色彩の世界へ踏み込んでいければと思います。
その際、ごく当たり前のことかもしれませんが、
最終的には個々の色を選ぶというよりも「それぞれの色(・素材)が組み合わさった時に生み出される全体の印象や効果」を選択する、ということを意識しています。(99 単色での判断ではなく、比較して関係性を見る p.227)
という部分のイメージ、どのようなものを目指すのかをより確かなものにしていくことが重要なんだろうなと思います。