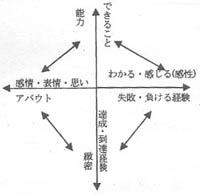B033 『建築の終わり―70年代に建築を始めた3人の建築談義』
建築はイデオロギーから直截な形態の問題となった。そして形態の問題は分かりやすいため容易に政治的権力や資本権力の道具になる。そんな状況に無自覚であることを僕は「建築の終わり」と感じている。
「建築とは制度的存在である」なんて、今の感覚ではずいぶん重たい話のように思えるのだが、そんなに簡単には社会の構造は変わらない。現在はさらに巨大な力の構造性のなかに取り込まれているために、そのメカニズムはみえないものとなっているだけなのだ。だから、行く先はみえない、建築はファッションと同じように軽くなり、どの建築もとりあえず消費されることを欲している。そんなとき、捨てられたカードを拾ってみよう。建築を始める切り札はある。
ギャラ間で開催された北山恒の展覧会にあわせて行われた、1950年生まれの三人による対談録。
卒業設計から今にいたるまで、その時代性を感じさせる赤裸々な対談は興味深い。
それぞれにスタンスの異なる三人ではあるが、書中で笠原が『意図的に広義の「普遍」や「秩序」において建築を捉え直そうとしている』と指摘しているように、建築を正面から捉えることをあきらめていない。
そのあたりが、おそらく彼らより若い世代との違いだろう(若い世代は別な視点から建築をあきあきらめない方法を模索しているのだろうが)
そのために、あえて『エッジに立つ』ことで建築を浮き上がらせるのが彼らの試みていることではないだろうか。
「小さな自由、大きな不自由」みたいなものがあるんですよ。大きな不自由については目をつぶりましょうということ。そうやって過ごしてきて、大きな話が見え始めているのが今なんじゃないかと思う。(内藤)
だけどそれを全部自分で一応自己決定できると思っているから、『TOKYO STYLE』みたいなインテリアがわっと出てくる。それは、本当に多様なバリエーションをもって、「私の自己決定でできた自分の空間」みたいなものとして捉えられている。だけどそれは大きな物語に対してなんら影響力がない。本当に小さな幸せ、小さな自由である。みんなそんなものだと思っている。(北山)
市民社会では、自分で自分のあり方を決定できる喜びがなくなってしまって、資本に飼いならされてしまっている。(北山)
内藤の『小さな自由、大きな不自由』にはおおいに共感する。
『小さな幸せ、小さな自由』でいいじゃないか、大きな物語に対して影響力をもつ必要性がどこにあるのだ、という意見もあるだろう。
しかし、それこそが『小さな自由』の危険なところである。小さな自由を餌に飼いならされている間に多くのものが奪われても気付かなくなってしまう。
そして、その奪われた状況を敏感に感じ取っているのが子供たちではないだろうか。
また、「建築⊃建築家」という集合が「建築⊂建築家」というように逆転しているという指摘も興味深い。
「建築」という概念そのものが商品化されつつある。
これから先は、小さな物語に対して大きな物語が侵入してくる時代だと僕は思うんです。そのときに、小さな物語の中で組まれた「建築」という概念は役に立たないと思う。(内藤)
これはおそらく若い世代にあてた大きな物語を捨ててはいけないという警告である。
しかし、若い世代も建築をあきらめたわけではない。
大きな物語を扱えるというのは幻想ではないか、逆に小さな物語を育てることで大きな物語に侵入していくという方法論もある、と言う立場もあろう。
大きなリスクを背負いつつも、今のネット上での小さな情報の伝播の速さ大きさを考えると、無視できない。
小さな物語の中の大きな、または大勢の問題児・反乱児が大きな物語を動かすかもしれない。(それすらも大きな物語(例えば資本)に吸収される可能性は大いにあるが)
うーむ。またもや判断に困ってしまう。
しかし、この本を通して強まった思いもある。
それは、個々のの持つ建築に対するイメージの強さ・重要さである。
やはり、彼らも論理に先立って何らかのイメージのようなものを持っていると感じた。
僕も「建築の始まり」のイメージを見つけ出さなくてはならない。
*************************
建築を設計するということはとりもなおさず、そして言うまでもなく、世界をどう認識するかということの表明でもあるわけで、どんなに批判されても僕は世界は秩序に満ちていて欲しいと願っているんです。(岸)
建築は地に足を付けていなければいけないんじゃないか。地に足を付けた上で頭で考えるからこそ建築なんじゃないか。宙に待ってしまったら、それは孤立した狭隘な概念でしかなくなると思う。(内藤)
「息苦しさ」というのは、たぶん個人の方に選択権がない状況、要するに建築の側から抑圧されている状況だと思うんだけれども、人間を抑圧していくというか、選択権を与えていかないような建築というものが、近代建築のたどってきた様相だとするならば、それとは違う組み立てはできるだろうと僕は思っています。(北山)
モダニティは否定できない、その結果現れるグロバリゼーションの否定できない、
となればそういうものを受け入れつつも、世界中どこであれそれぞれの場所で生きている人間の誇りやそれが依って立つその場所の記憶といったようなものの最後の防波堤に建築がなるしかないんじゃないかと思っている。形あるものは必ず消費の対象になる。攻撃される。だから、そうした大きな流れに対抗するための最大の武器は、目に見えない空間の強度、つまり空気感、といったところかな。そんなものを追い求めて生きたい。(内藤)

 竹原義二(彰国社)1997.03
竹原義二(彰国社)1997.03


 篠原哲雄監督長谷川康夫脚本(岩波書店)2004.03
篠原哲雄監督長谷川康夫脚本(岩波書店)2004.03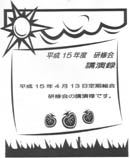 中村隆司講師(バリアフリー研究会?)?
中村隆司講師(バリアフリー研究会?)?