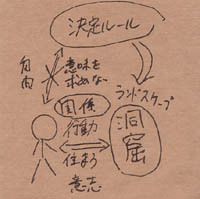B092 『コート・ハウス論―その親密なる空間』
僕が生まれる前の年の本。
コートハウスについて論じられているのだが、図版つきで具体的に書かれているので解りやすく今でも十分に参考になる。
著者によるとコートハウスに期待するところのものは
敷地全体を、庭と室内を含めて、あますところなく住居空間として企画し、屋外にも残部空間を残さない住居であり、囲われた敷地の中に自然と人、室内と室外の緊密な関係を造り出す
ことにある。
このことは、僕が住宅に期待する大きな要素でもあるのだが、それは近代建築の作法や伝統的な日本建築の知恵などと重なる部分も多い。
しかし、周りを見渡すととてもコートハウスやコートハウス的思想が定着しているとは思えない。
住宅を快適にするにはかなり有効な方法に違いないのになぜだろうか、と考えるといくつか理由が考えられる。
一つは、日本の敷地の取り扱い方がコートハウスを困難にしている事にある。(民法では近隣の合意が得られない限りは隣地境界線から50cmは建物を離さなくてはいけない)
もう一つは、コートハウスは敷地の形状や特性に合わせていろいろな工夫をする必要があり、メーカー住宅などの規格化に向かない事にあるように思う。
規格化するためには、内外の緊密な関係などに興味を持たずに住宅というパッケージの中身だけで満足してもらっているほうが都合が良いのだ。(規格化というのは特別な工夫が要らず誰でもつくれる、ということでもある)
さらには、現代の近視眼的な傾向もコートハウスが目を向けられない要因の一つであると思う。というか、近視眼的な住宅・生活環境が人々を近視眼的にしているという側面もあると思うのだ。
建築を学んでいてコートハウスに魅かれない人はなかなかいないと思うのだが、それがなかなか一般の人に共有されていかないのはやっぱり少し寂しい気がする。
MEMO
■住宅はどこまでも外界から隔絶された絶対個人の空間でなければならない。そして敷地が広くない場合、自然を100パーセント楽しむためには敷地全体が庭であり、同時にまた住居空間でなければならない。
■住宅は劇場でも教会でも料理屋でもないから、そのような驚きを住む人にあたえることは禁物である。住む人はなんの心の抵抗もなく住めなければならない。しかしこのことは住宅が無性格であったり、無気力なものであることに通じるのではない。住宅は住む人びとに快い安らぎを与え、未来の飛躍に向かって前進すべき人柄のなかへと、ちょうど太陽が生きとし生けるものの身にしみわたっていくように浸透していくべき性質のものであらねばならない。
■サーキュレーション・チャンネルとして使われる廊下はできるだけ少なく、またその部分でも変化が楽しまれ、これにぶらさがる個人のプライバシィをその必要度に応じて保ちながら廊下から居間へ、居間から個室へと移りゆくに従って変化ある庭がもてるようにというのが私が住宅を設計する場合の願いである。
住宅が外部に対してオープンであるべきかどうかという事を悩んだりもするが、それは実は通りに対してもさして重要でないのかもしれない。
散歩をしていてなんとなくいい感じの家だなと思うのは、塀などで囲われていても、その中の庭や家の中での豊かな時間の流れが想像できるものが多い気がする。
そういう家は、住宅そのものがその敷地に対して安心して座り、満足しているような感じを受ける。それが、敷地の上に無造作に置かれ、さらし者にされているような家ではやっぱりあまりよい印象を受けない。敷地の上で住宅それ自信が安心し、楽しんでいるか。そのような見方も建物の良否を見分ける基準になるかもしれない。














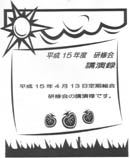 中村隆司講師(バリアフリー研究会?)?
中村隆司講師(バリアフリー研究会?)?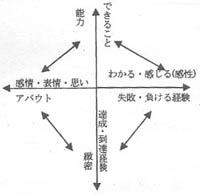


 あるきっかけがあり「屋上」と「自由」について考えてみたくなった。
あるきっかけがあり「屋上」と「自由」について考えてみたくなった。