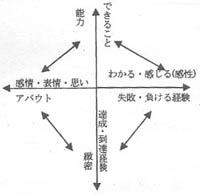佐々木 正人 (編集)
佐々木 正人 (編集)
東京大学出版会 (2013/6/29)
以前3回にわたって感想を書いた『知の生態学的転回』の第1巻。
先にこのシリーズ3巻の部構成を引用しておく。
1 身体:環境とのエンカウンター
序章 意図・空気・場所――身体の生態学的転回
第I部 発達と身体システム
第II部 生態学的情報の探求
第III部 生態心理学の哲学的源流と展開
終章 魂の科学としての身体論――身身問題のために
2 技術:身体を取り囲む人工環境
序章 知覚・技術・環境――技術論の生態学的転回
第I部 環境に住まう
第II部 アフォーダンスを設計する
第III部 21世紀の技術哲学
終章 技術の哲学と〈人間中心的〉デザイン
3 倫理:人類のアフォーダンス
序章 海洋・回復・倫理――ウェザー・ワールドでの道徳実践
第I部 生態学的コミュニケーション
第II部 人間のアフォーダンス
第III部 社会的アフォーダンス
終章 可能性を尽くす楽しみ,可能性が広がる喜び――倫理としての生態心理学
[座談会] エコロジカルターンへの/からの道
2の技術は人が環境との関わりの中から技術がどのようなあり方であるかが書かれていたように思うが、今回はその前段階として発達や進化、意識といった人と環境との関わり、認知や知覚について書かれていたように思う。そして、第3巻は複数の人によって構成される社会へと射程が拡がっていくようだ。
心身二元論と環境との境界を超えたイメージ
知覚について多くの人は、環境から刺激を受け取り、それを脳が処理し、その結果行為が行われる、また、発達などは予めプログラムされた結果である、というようなコンピューターや機械に似たイメージを持っていると思う。
この巻の「転回」はそのイメージからの脱却することにある。
そのイメージをここで説明するのは難しいし専門ではないので正確に捉えられている自信はない。
それでも書いてみると、動物が能動的に環境に働きかけ探索しながら情報をピックアップしていく過程で、身体と環境、行為と知覚が同時に進みながら新たな行為と知覚が紡がれていくというようなイメージだ。その基盤は環境と身体に埋め込まれている。どのような行為に繋がるかは予め厳密に決められているというよりはその都度発見されていくような動的なシステムなのだと思う。
そこではデカルト以来の心身二元論と環境との境界が超えられている。(そして、もしそれがより可能性のある考え方だとすると、デカルト的心身二元論に基づいた今の教育は少し古臭い気もするし、固定的なイメージを植え付けているという点で罪悪ですらある気もする。)
子どもと生き物に関する番組をよく見るが、どうしてそのように振る舞えるのか不思議に思うことが多い。
例えば、アルコンゴマシジミの幼虫はアリの巣に潜り込みアリの幼虫になりすまして世話をしてもらい蛹となって羽化する。さらにエウメルスヒメバチはこのチョウの幼虫が忍び込んでいるアリの巣を感知しこのチョウの幼虫に卵を産み付け寄生する。
アリの巣でせっせと育てられたチョウの蛹が更に食い破られて中からハチの成虫が出てくるような、もう笑ってしまうような複雑な生態を見ると、本能ってなんだろう、あの小さな体にどこまで複雑なプログラムが埋め込まれているのだろうと想像してくらくらしてしまう。(ツチハンミョウの幼虫の生態も同様にクラクラする。)
しかし(この本で本能については書かれていなかったが)仮にそのような生態の基盤が環境と身体と欲求の中に埋め込まれていると考えると何かしっくり来た。例えば、アリに育てられているチョウの幼虫という環境が存在し、その幼虫を感知するような身体を備えたハチが、そこに卵を産みたいという欲求を持つとすると、本能によって緻密にプログラミングされていなくともこういった複雑な生態が成り立つような気がした。そのハチにとっての意味が環境自体に備わっていると言えるが、それは異なる生態にとっては異なる意味となる。さらに、身体に含まれる自由度が環境の変化によって異なる関わり方を生み出すこともあるだろうし、それが進化と繋がることもあるだろう。(選択交配とは異なる進化の可能性もこの本で触れられていた。)
少し脱線したが何が書きたかったかというと、知覚や行為において環境と身体の境界は曖昧でダイナミックな関係にあるということである。その「転回」の面白さはデカルト以降の科学感が染みこんだ頭ではすぐに見失ってしまうのだけども。
設計との関連
さて、これらの「転回」は設計とどのような関連があるだろうか。言い換えると設計にどのような「転回」が起こりうるだろうか。
大まかなイメージは掴めつつあるのだが具合的に設計に落としこむところまで行けていないのでもう少しイメージの精度を高めていく必要がありそうだ。
以前書いた技術に関することと一部重複するかもしれないが、整理するために今回の本に関連して思いつくことを列挙しておきたい。
・隈研吾のオノマトペ
■オノケン【太田則宏建築事務所】 » B183 『隈研吾 オノマトペ 建築』
プロセスにおいても現れにおいても、その足がかりとしているのがオノマトペのようだ。
この二面角の定義では、二つの面の配置が私たちにアフォードすることが述べられている。『生態学的知覚論』で挙げられた面の配置の用語は、そのリストアップと定義の方法が今ひとつ不明瞭であるものの、確かに言えるのは生態幾何学の用語が知覚-行為にとって意味のあるレベルで環境を記述する可能性を持っているということである。(本書p77)
一つはギブソンの生態幾何学的な環境の捉え方をそのまま建築の形態へと翻訳することで、隈さんのオノマトペはそれを実践したものであると言えそうだ。
また、スタッフにオノマトペの曖昧な言葉を投げかける設計手法は生態的な探索過程の実践的置き換えと言えるだろう。
ギブソンの『生態学的知覚論』は専門的な実験過程が詳細に書かれていて読むにはかなり大変だろうと予想していたため後回しにしていたけれども、思い切って購入してみると思っていたより遥かに読みやすそうなので一度じっくり見てみようかと思う。(こんなことならもっと早く読むべきだった。)
■オノケン【太田則宏建築事務所】 » B177 『小さな矢印の群れ』
隈さんの本に佐々木正人との対談が載っていた。建築を環境としてみなすレベルで考えた時、建築を発散する空間と収束する空間で語れるとすると、同じように探索に対するモードでも語れるのではと思った。 例えば、探索モードを活性化するような空間、逆に沈静化するような空間、合わせ技的に一極集中的な探索モードを持続させるような空間、安定もしくは雑然としていて活性化も沈静化もしない空間。など。 隈さんの微分されたものが無数に繰り返される空間や日本の内外が複層的に重なりながらつながるようなものは一番目と言えるのかな。二番めや三番目も代表的なものがありそう。 四番目は多くの安易な建物で探索モードに影響を与えない、すなわち人と環境の関係性を導かないものと言えそう。この辺に建物が建築になる瞬間が潜んでいるのではないか。 実際はこれらが組み合わされて複雑な探索モードの場のようなものが生み出されているのかもしれない。建物の構成やマテリアルがどのような探索モードの場を生み出しているか、という視点で建築を見てみると面白そう。
直接的に探索モードの場、というイメージを空間に重ねることも生態幾何学的な環境の捉え方を建築の形態へと翻訳することに繋がるかもしれない。
・地形のような建築
まず、(地形)は(私)と関係を結ぶことのできる独立した存在であり環境であると言えるかと思います。 (私)に吸収されてしまわずに一定の距離と強度、言い換えれば関係性を保てるものが(地形)の特質と言えそうです。 この場合その距離と強度が適度であればより関係性は強まると言えそうです。(オノケン【太田則宏建築事務所】 » 「地形のような建築」考【メモ】)
だいぶ前に書いた地形のような建築は、(私)との関係性を保てることが一つの特徴だと考えていたのだが、これは言い換えると探索の余地、もしくは身体と環境、行為と知覚が動的な生態学的関係を結べる余地とでも言えるだろう。
・塚本由晴のふるまいと実践状態
その木を見ると、木というのは形ではなくて、常に葉っぱを太陽に当てよう、重力に負けずに枝を保とう、水を吸い上げよう、風が吹いたらバランスしよう、という実践状態にあることからなっているのだと気がついた。太陽、重力、水、風に対する、そうした実践がなければ生き続けることができない。それをある場所で持続したら、こんな形になってしまったということなのです。すべての部位が常に実践状態にあるなんて、すごく生き生きとしてるじゃないですか。それに対して人間は葉、茎、幹、枝、根と、木の部位に名前を与えて、言葉の世界に写像して、そうした実践の世界から木を切り離してしまう。でも詩というのは、葉とか茎とか、枝でもなんでもいいですけど、それをもう一回、実践状態に戻すものではないかと思うのです。(中略) 詩の中の言葉は何かとの応答関係に開かれていて生き生きとしている。そういう対比は建築にもあるのです。窓ひとつとっても、生き生きしている窓もあれば、そうでない窓もある。建築には本当に多くの部位がありますが、それらが各々の持ち場で頑張っているよ、という実践状態の中に身を置くと、その空間は生き生きとして楽しいのではないか。それが、建築における詩の必要性だと思っています。( 『建築と言葉 -日常を設計するまなざし 』)(オノケン【太田則宏建築事務所】 » B174 『建築と言葉 -日常を設計するまなざし 』)
なぜふるまいなのか 20世紀という大量生産の時代は、製品の歩留まりをへらすために、設計条件を標準化し、製品の目標にとって邪魔なものは徹底して排除する論理をもっていた。しかし製品にとっては邪魔なものの中にも、人間が世界を感じ取るためには不可欠なものが多く含まれている。特に建築の部位の中でも最も工業製品かが進んだ窓のまわりには、もっとも多様なふるまいをもった要素が集中する。窓は本来、壁などに寄るエンクロージャー(囲い)に部分的な開きをつくり、内と外の交通を図るディスクロージャーとしての働きがある。しかし、生産の論理の中で窓がひとつの部品として認識されると、窓はそれ自体の輪郭の中に再び閉じ込められてしまうことになる。 (中略) 窓を様々な要素のふるまいの生態系の中心に据えることによって、モノとして閉じようとする生産の論理から、隣り合うことに価値を見出す経験の論理へと空間の論理をシフトさせ、近代建築の原理の中では低く見積もられてきた窓の価値を再発見できるのではないだろうか。(『WindowScape 窓のふるまい学』)(オノケン【太田則宏建築事務所】 » B166 『WindowScape 窓のふるまい学』)
塚本さんのふるまいや実践状態という言葉にも生態学的関係への意志が見てとれる。モノとヒトに対する眼差しの精度を高めることによって生態学的関係を開くようなモノのあり方へと導いていくことができるはずだ。島田陽さんの建築の部分を家具的に扱うこともこれに関連するように思う。
・ニューカラー的な建築
イメーシとしては、ブレッソン的な建築と言うのは、雑誌映え、写真映えする建築・ドラマティックなシーンをつくるような建築、くらいの意味で使ってます。一方ニューカラー的というのはアフォーダンスに関する流れも踏まえて、そこに身を置き関り合いを持つことで初めて建築として立ち現れるもの、くらいの意味で使ってます。 設計をしているとついついドラマティックなシーンを作りたくなってしまうのですが、それを抑えて、後者のイメージを持ちながら建築を作る方が、難易度は高まりそうですが密度の高い豊かな空間になるのでは、という期待のようなものもあります。(オノケン【太田則宏建築事務所】 » B175 『たのしい写真―よい子のための写真教室』)
関り合いによって初めて建築として立ち現われるものをイメージすることも生態学的関係を志向することなるように思う。それは隈さんのいう反オブジェクトとも重なるし、そのためにそのイメージを維持し続ける必要があるだろう。
・分かることへの距離感を保つ
他方で僕は、何かをわかりたいと同時に、わかってしまうことが怖いのだ。(中略)わかろうとすることと、わかってしまうことを畏れることは矛盾する。その矛盾を自ら抱え込むことが、わかることの質を高めてくれる気がする。(オノケン【太田則宏建築事務所】 » B173 『考えること、建築すること、生きること』)
寺田寅彦が「不思議のさなかを生きる」少年のモードを維持することの肝は、説明し分かったことにしない、「多様な現象を見る眼」にあるようだ。 寺田寅彦の思考法として、「問いの宙吊り」「アナロジー 原型的直感」「像的思考」を挙げている。(オノケン【太田則宏建築事務所】 » B182 『〈わたし〉の哲学 オートポイエーシス入門 』)
分かることへの距離感も保ち続けること、少年のモードを維持し自在な建築を目指すことはおそらく生態学的関係を開くことへと繋がるように思う。
・設計プロセスの工夫
なので、フォロアーの劣化版になることを怖れず、これを機会に自分なりにカスタマイズし消化することを試みてみたいと思う。(オノケン【太田則宏建築事務所】 » B180 『批判的工学主義の建築:ソーシャル・アーキテクチャをめざして』)
動的で生態学的関係を考える際には必ず藤村さんが頭に浮かぶのだが、そのプロセスにはそのような関係の発生が埋め込まれている。(そして、その部分で氏の「建築」に可能性を感じている。)
しかし、まだしっくりとした自分なりのプロセスの設計ができていないというのが現状である。
クライアントや環境、その他与件に対して探索と応答を繰り返す普通の設計を誠実にこなせばいいとも思うのだが、その精度を高める工夫は必要だろう。
・都市的な目線
現状、自分に最も不足しているのが都市的な視点であるように思う。これまで書いたことは主に建築の空間をイメージしているが、生態学的関係を都市へと開いていくようなことは可能だと思うしそれによってまちなみはより楽しく豊かなものになるだろう。
そのために長谷川豪さんの建築内部と都市を貫くような視点を持つことも必要だろうし、実践状態が街を行く人に感じられるような表出の仕方も考える必要があるだろう。
まとめ
まとめると、
生態幾何学的な環境の捉え方を建築の形態へと翻訳したり、モノへの眼差しの精度を高めながら生態学的関係を開くようなモノのあり方へと導きつつ、分かったことなったり建築がオブジェクトになることを避ける姿勢を維持しながらそれらを実現できるプロセスを考え、更にはその視線を都市へと拡張していく。
となるだろうか。
また、生態学的関係を開く上で関連があると思われるが、まだ明確な言葉にできていないことを課題という意味も含めて挙げておく。
・「住まうこと(つかうこと)」の中に「建てること(つくること)」を取り戻す
建築の、というより生活のリアリティのようなものをどうすれば実現できるだろうか、ということをよく考えるのですが、それに関連して「建てること(つくること)」と「住まうこと(つかうこと)」の分断をどうやって乗り越えるか、と言うのが一つのテーマとしてあります。(オノケン【太田則宏建築事務所】 » ケンペケ03「建築の領域」中田製作所)
「建てること(つくること)」の中にも生態学的関係への可能性があるように思う。
・既知の中の未知との出会いのセッティング
僕は、アートといいうものがうまく掴めず、少なくとも建築を考える上では結構距離を置いていたのですが、アートを「既知の中の未知を顕在化し、アフォーダンス的(身体的)リアリティを生み出すこと」と捉えると、建築を考える上での問題意識の線上に乗ってくるような気がしました。(オノケン【太田則宏建築事務所】 » B178 『デザインの生態学―新しいデザインの教科書』)
創造に関して、「発見されたもの」すなわち結果そのものを作ろうとするのではなく、「発見される」状況をセッティングする、という視点を持ち込むこと。 それは発見する側の者が関われる余白を状況としてつくること、と言えるかもしれないが、このことがアフォーダンス的(身体的)リアリティの源泉となりうるのではないだろうか。 (ここで「発見」を「既知の中の未知との出会い」と置き換えても良いかもしれない。) そういった質の余白を「どうつくるのか」ということを創造の問題として設定することで、発見の問題と創造の問題をいくらかでも結びつけることができるような気がする。(オノケン【太田則宏建築事務所】 » B179 『小さな風景からの学び』)
既知の中の未知との出会いをセッティングすることは高度な手法であるかもしれないが、それゆえに精度高く生態学的関係を開くことができるように思う。
・内発的制約と熟達化
ストリートダンスの熟達化とは、このような内発的制約からの自由を獲得し、同時に多様で洗練された表現への自由を獲得することであるといえる。(本書p125)
リズムに合わせて膝をダウン又はアップさせる実験では、テンポを早くすると非熟練者はアップ課題においても意に反してダウン動作になってしまうそうだ。「熟達化とは、このような内発的制約からの自由を獲得」することであるという指摘は当たり前のように思える。しかし、それが力任せなものではなく、人と環境との関係の精度を高めることで冗長性と自由度を獲得するという点で新鮮に映った(イチローのバッティングが頭に浮かんだ。)。では、設計や空間における熟達化とはどのようなものだろうか。何が内発的制約となり、そこから自由になることでどう変わり得るだろうか。
 河本英夫(著)
河本英夫(著) 『損傷したシステムはいかに創発・再生するか: オートポイエーシスの第五領域』
『損傷したシステムはいかに創発・再生するか: オートポイエーシスの第五領域』







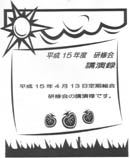 中村隆司講師(バリアフリー研究会?)?
中村隆司講師(バリアフリー研究会?)?