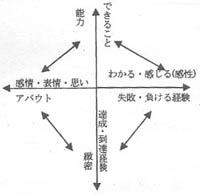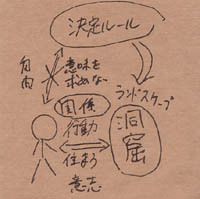小巻 哲 , ギャラリー間 (編集)
小巻 哲 , ギャラリー間 (編集)
TOTO出版(2003/07)
ギャラリー間の100回目の展覧会を記念して行われたシンポジウムの記録。
各世代から1人ずつ、5世代5人によるセッションが5回行われた。
各セッションの参加者は
1.原広司(1936)、伊東豊雄(1941)、妹島和世(1956)、塚本由晴(1965)、吉村靖孝(1972)
2.磯崎新(1931)、山本利顕(1945)、小嶋一浩(1958)、千葉学(1960)、山城悟(1969)
3.石山修武(1944)、岸和郎(1950)、青木淳(1956)、阿部仁史(1962)、太田浩史(1968)
4.篠原一男(1925)、長谷川逸子(1941)、隈研吾(1954)、西沢立衛(1966)、藤本壮介(1971)
5.槇文彦(1928)、藤森照信(1946)、内藤廣(1950)、曽我部昌史(1962)、松原弘典(1970)
(括弧内は生まれた年)
必ずしも「この先の建築」のビジョンが明確に描き出されたわけではない。
しかし、世代間で建築や社会の感じ方やスタンスに違いがあるものの、全体としてはぼんやりとした方向があるように感じた。
それは例えば「個」や「自由」という言葉に含まれるイメージのようなものである。
「この先の建築」に当然だが確固とした正解があるわけではなく、それは各個がそれぞれ考え実践する中で全体として描き出されるものだということ、 まさしくこのシンポジウムの形式そのものが浮かび上がってきたように思うのだ。
正解があらかじめ用意されているのではない。
この本で最も印象に残ったのはシンポジウムに参加できなくなったために書かれた、伊東豊雄の手紙である。
私が今建築をつくることの最大の意味は「精神の開放」です。平たく言えば、人びとが真にリラックスして自由に楽しめる建築をつくることです。しかし今、日本は建築をつくることにきわめて不自由な社会に思われます。発注者もつくり手も、皆が金縛りにあったように相互監視にばかり夢中になり、何をつくるべきか、なぜつくるべきかを見失っています。私が若い建築家に期待するのは、もっとプリミティブな視点に立ち返って「あなたはなぜ建築をつくるのか」という素朴な問いに答えて欲しいことです。そうでない限りこの自閉的な状況をくぐり抜けることはできないし、ましてや「この先の建築」など望むべくもないように思われます。(伊東豊雄)
「つくる」ということはどういうことか、「つくる」ためにはどうすればよいか、そこに立ち戻ったうえで組織のあり方や関係、具体的な手段などもう一度きちんと考え直さなければならない。
*****以下各セッションから*****
1.
建築のデザインが、あるいはそのデザインがもっている論理性というものは、人びとにたいしてどこまで射程があるのか(原)
(MVRDVについて)自分の外部にある何かを調べることで、自分の立ち位置をよりシャープにしていくという作業を繰り返しているのです。テリトリーをただ闇雲に拡大していくというよりは、建築家が本当にやるべきことは何か、何ができるのかということを、常に自問しているという印象をもちました。(吉村)
僕が妹島さんの建築がすごくいいと思うのは、集落がもっているエレガントなものを、今のデザインで、所帯じみていない形で出してくるからです。
僕はかつてのコミュニティ論なんていうものを、あなたたちが本気になって打破せよといいたい。・・・都市の中に埋没していく、あるいは地縁や血縁や昔のコミュニティだとかいった社会の中に埋没していくのではなく、生活が可能なところで出てくるような身体的な心地よさがあると思います。(原)
今までの経験から言うと、世の中を良くしようと思うとろくなことはないんですね。世の中を良くできるなんて思わないで、自分がうまく生きるということでいいと思います。建築家は人の家をつくるわけですから、建築家としては常に他者に対する思いやりというものを何らかのかたちで表現していくことが重要なような気がします。(原)
1.補
で、なぜつくるのか。先日のシンポジウムでは、建築家として都市にどうアプローチするつもりかといった質問がされていましたが、僕はそんなことはどうだっていいやと思っています。・・・僕は建築をつくり続けてきたから、自分の考えていることをたまたま建築によって表現するだけであって、まず僕が建築をつくりたいと思うのは、建築というフィルターを通すことによって、自分が今の社会の中で何をしなければいけないかとか、何を考えなくちゃいけないかということが少し見えるような気がするからですね。(伊東)
2.
いまだに世の中は計画というものがまだあると信じているところがあって、これが世の中をムチャクチャにしていると僕は思っています。(磯崎)
建築がその国や社会を体現するものとしてではなく、より個人的な人間の身体的な部分との関係の中で位置付けられようとしている(千葉)
先ほど磯崎さんが言いかけた「計画」という話は、個人の責任をどんどん曖昧にしていく。個人が関わるべきものであるにもかかわらず、あらかじめ「計画」という概念があって、最適値がもともとあるんだと考えて、その「計画」に乗ろうと思ったわけですね。そこでは個人がどんどん抽象化されてきて、個人という関わり方ができなくなってくる。(山本)
その使い方のきっかけになるようなもの、それを僕は最近「空間の地形」と読んでいるのですが、その地形をどうつくっていけるのかが今後ビルディングタイプに頼らない一つのアプローチだと思っています。(千葉)
文化的に刷り込まれてしまった身体を偶像破壊して、そのようにカテゴライズされてしまった身体をさらに解体するということをやっていかないと、生々しい身体になかなかたどり着けない。(山本)
3.
マーケットと直接的に結びつく方法をもたなければダメだと思っています。今までの建築ジャーナリズムは、この側面では役に立たない。もうちょっと広範な、そして非常にダイレクトなコミュニケーションの仕方をマーケットとの間でもたないと、これからは進めようがない(石山)
そのとき機能とは空間をある一定の方向に追い込むための一種のアリバイにすぎないのではないか。(青木)
自分にとって切実な問題を超えて正論を言うのはずるいですね。どうして身の丈でやれないのかなぁ。とにかく、そういうことを、少なくとも僕より若い世代にはもうやって欲しくないなあと思います。(青木)
今の世の中はこうだからという言い方は、僕は嫌ですね。何かをつくることから、結果として一般論みたいなものが出てくることはよくあることですが、先に一般論があって、その適用として個別の建築があるというのはもういいのではないですか。(青木)
どうやって食っていったらいいのかというと、設計図がもっている意味をもうちょっと拡大すればいいんだということになるわけで、建築設計がデザインだけではないところにまで踏み込まざるを得ないのではないかと考えています。(石山)
4.
新しい建築のための5つの問い
■住むための「場」:機能主義的な機械としてではなく、より根源的な「住むための場」をつくること。「場」は「きっかけ」「手掛かり」といってもいい。新しい原始性の模索
■不自由さの建築:何もない不自由さではなく、人間にとって「自然」のような、行動を喚起する、快い異物の不自由さ。
■かたちのない建築:機能的にも、存在としても、自律していないこと。完結していないこと。不完全性のもつ可能性。都市。
■部分の建築:全体性を規定せずに、部分から建築を構想することで、今までとは全く異なる、複雑さ、不完全さの建築を生み出すことができるかもしれない。
■弱い建築:複雑さ、多焦点、分散、隣接関係、相対性、不自由さ、不完全性、曖昧さ、喚起する、新しい原始性・・・。
(藤本)
囲碁とか天気予報と言っているときはダイナミックで面白い話なんだけれども、それを建築というものに落としてきたときには、どうなるのだろう。固定してしまうものなのか、あるいは動いて装置のようになっていくのか。最終的に建築にどう到達させようとしているのか(藤本)
私は「かたち以外のことを考えたことがない」(篠原)
最も激しい象徴性と最も強い具体性とが一つになったものが「野生」であるということです。(『野生の思考』レヴィ=ストロース)(篠原)
50年前からの各断面で私がお話しようと思ってきたことの一つは、その時点での自分の「今」が、何かのメカニックで「この先に」変わってきたことです。(篠原)
常にさかのぼっていきたいという気持ちがあるんですね。それは未来のことを考えるときにでも、ある種のプリミティブな状態に立ち返って、今までに試みられなかったことがないもののつくり方で、もう一回全部を構築し直したいという思いがあります。(藤本)
5.
そうしてつくりだされたビジョンが、嘘っぽくてリアルじゃないと分かっていても、そればかりを公共投資でやってきている。だから、再生のシナリオとは違う方向があるのではないか。(内藤)
素材の向こうに先端のエンジニアリングを見たり触れたりしたい(内藤)
当面感のある建築は、たいていの場合、抽象的なイメージを建築として再現しようとした結果だと思うんです。・・・僕らのやり方としては、そういう、いったん抽象化するプロセスには実はあまり興味がなくて、よりダイレクトに社会に反応することで建築をつくりたいという気持ちがずっとしています(曽我部)
「愛着のプロデュース」という言い方にすごく興味がある・・・「建築に何が可能か」ということよりも、「建築家に何が可能なのか」という問題設定ではないかと思います。(曽我部)
説明できることは流通しやすいことで、本当に大切なことは、どうあっても説明できないことではないか。つまり、建築家の一番のコンテンツは、建築の中にしかなくて、言葉の中にはない。(内藤)
建築には無意識の世界―言語化できない世界―に働きかける力があると思っているんです。・・・だから、今の日本の街並みによって無意識の世界がつくられていくのは良くないなという感じがします。(藤森)
同潤会に対しては、歴史としてみてしまう。それは歴史上のある特異点であって、その特異点を美しいオブジェクトとして見ることもできるという理解です。団地というものは、僕にとって、もう少し肉体化されているというか、歴史上の特異点ではなくて、なじんだ風景であり、引き受けざるを得ないようなもの(松原)
(『文学における原風景』奥野健男より)その次の問いが面白くて、ではそういう原っぱも路地もなくなってしまった世代は、一体何が原風景なのかと。彼らにとってはもっと無機的なものではないか。あるいは団地の風景でもいいけれども、彼らには風景の叙述がないんですね。いきなり部屋の中での会話で始まるということを言っています。(槇)
藤森さんは絶望したけれども、見ようによっては悪くない、と皆で言い訳しながらやってきたわけですよ。・・・だけど「それは本当なのか?」ということをもう一度考えたほうがいいのではないかと僕は思っているんです。
・・・たぶん建築が人間社会に対してできる究極は、例えば社会が経済的なクラッシュで疲弊し、人間も疲れ果てたときに、僕達が今やっている仕事が何の支えになるのかということが、建築のきわめて本質的な役割なのではないか、街をつくったりすることの役割なのではないかと思うんです。(内藤)
先ほどから東京の街が美しい、いや美しくないという議論がありますが、どっちも当たっているんですよ。・・・(須賀敦子のように街全体が生き物であるかのような見方、愛のある目差し)そういうかたちで街を見ることができるセンシティヴィティが、これからわれわれがどの街に住み、ものをつくり、あるいは旅行するにあたっても大切だと思います。(槇)















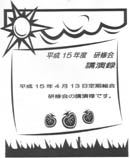 中村隆司講師(バリアフリー研究会?)?
中村隆司講師(バリアフリー研究会?)?