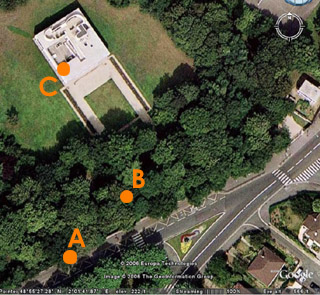このごろずっと疲れがたまっていて、何をやってもうまくいかない。
その原因はおそらく『焦り』だ。
僕と同年代の建築家がいっせいに活躍を始めだしている。
スターダムに上り詰めることを目差しているわけでは全然ないけれども、自然と自分と比較し焦りを感じてしまう。
僕自身、自分でやろうと思っていることと現実のギャップを感じ焦りを感じてしまう。
他人の『焦り』は客観的に見えるし、焦りのマイナス面もよく見える。
しかし、自分の中の焦りをコントロールすることはなかなか難しい。
焦りは空回りを生んで、マイナスにしかならないと頭では分かっているけれど、そう思えば思うほど焦りが増す。
きのう、それが原因で妻とちょっと言い合いになった。
もう一度、自分を見つめなおそう。
「今日出来ることは明日に延ばすな」という格言がある。
今までは、それを続けることで未来を拓けると信じていた。
しかし、時間には限界があり、自分の中でイメージする今日出来ること、今週できること、今月出来ること、今年出来ること、と現実とはギャップが生まれる。
そして、『今日出来るはずのこと、今日までに出来たこと』はどんどん蓄積されて、現実とのギャップは増すばかりになって、いつも何かに追われているような気持ちになっている。
身の周りの大切なことをなおざりにまでして今日やれることをやろうとしても、そのギャップは埋まらずに、焦りと共に罪悪感までが増してしまう。
焦りと罪悪感でがんじがらめになってしまった。
それで、良いわけがない。
そんなでは、良いものがつくれるようになれるわけがない。
なんとか、この悪循環から抜け出さなくては。
『今日やれることを明日に延ばすな』
背中を押してくれるよい言葉ではあるが、いつでも誰にでも効果があるというわけではないのではないか。
「今日やれることをやる」こと自体が目的ではないはずだ。
この言葉が単に自分を縛る規範になってしまったのなら、その規範は崩す必要がある。
『明日やれることは明日やれ』
これは、どこかで聞いたことがある。
でも、自分にはいまいちしっくりこない。
もうちょっとやわらかくしてみる。
『明日やれることは明日やっても良い。今日やることをやる』
こう考えるとちょっと楽になった。
『今日やれることをやれ』と『今日やることをやる』の違いは微妙だけれども僕にとっては大きい気がする。
やれることをすべてやろうとするんじゃなくて、今日大切なことを選んでやる。
いつもどこかで時計を気にしながらではない生活を心掛けてみよう。
『今日やれることを明日に延ばすな』ではなくて
『明日やれることは明日やっても良い。今日やることをやる』
これでも未来は拓けることを実証してみたい。
それを前提としたプランにすればよい。
ストイックであることに逃げ込むのはそろそろ卒業にしよう。
『明日やれることは明日やっても良い』
って仮説。
今日もひとつ大人になった。(ローカルネタです)
今日は昨夜眠れず寝不足なので仕事を早く切り上げて帰宅した。
妻は実家なので、家で一人なのだが、今日はせっかく早く帰ってきたんだからと、勉強はやめて仮眠・料理・風呂・洗濯・掃除・(自分で)散髪その他、とやりたいことをいろいろやろうと思った。
えーと、何時まで仮眠をとって、何時までに風呂と散髪と洗濯を終わらせて・・・・
あれ、これではまた時間に追われるではないか。
ひとつ大人になったのではなかったか。
ということで今日はふたつのことを明日に延ばす。
・掃除機までかけようと思ったけど、掃除は明日にする。
・いつもは明日の弁当までつくるのだけれども、今日は超手抜き料理(目玉焼き豆腐丼)にして、あしたはご飯だけ持っていく。おかずは弁当屋で。
いぇーい、今日はなんか余裕。
ようやく大人になれもした。